| Blog | |||||||
|
|
| |
|||||||
| 06/10/03 | 現実感がない。 疲れ切って、さらに風邪気味なのでそうなのだろうか。 以前にも書いたのだが、過去がうまく思い出せない。 いや、思い出せても、手応えがない。 自分はこの二十数年間何をしてきたのか、これをしたという皮膚感覚がない。 ひょっとしたら、自分は死に近いのではないかと思ってしまう。 と、夕飯を食う前は思っていたのだが、夕飯と酒を口にしてしまえば、そんなことも切実ではなくなってしまう。 手ざわりがないのは変わりはしないのだけれど。酔いのおかげなのか、どうなのか。 「現代詩手帖現代詩新人賞」は、一次選考にも漏れてしまった。 六百あまりの応募から、数十が予選通過という、たぶん十分の一の選考だったようだ。 選に漏れたことは口惜しい。 私の詩が、どれだけ特殊であるかということであろう。 悔しまぎれのへらずぐちではあるが、 私は言葉によって何かを描こうとはしていない。 言葉をつづることが、何かを指し示している。 「指が月をさすとき、愚か者は指を見る」と言うが、 私はその指を描いているのだ。 私が言葉で描いている世界は、じつは私の伝えたい世界ではない。 言葉の重なりがもたらす「響き」だけが、私があなたに伝えたいすべてだ。 これまでもここに書いてきたが、 私たちが気をつけなければならないことは、 言っていることが正しければすべてが正しいと思いこむことだ。 言っていることが正しくとも、言い方が正しくなければ疑わなければならない。 平和を神聖視する思想が、戦争を神聖視するのと同じ言い方で語られるならば、 私たちはその平和を疑わなければならない。 詩、というより、言葉は、 言葉が指し示す何かよりも、 指し示すその指の形にすべての思想が表れているのだ。 私たちは、たとえば高村光太郎や三好達治たちの「戦争協力詩」を弾劾するが、 私たちが相手にすべきは、言葉の重なりが何を伝えているかなのだ。 戦争協力者はいかようにされて排除されてもかまわないというのが、平和主義者の言であるなら、平和主義者と戦争協力者との間にどれほどの差があるというのか。 だから、私は言葉が指し示すものをそれほど信じはしない。 言葉がどう使われているかだけが、言葉の重なりが伝える「響き」だけが、 私の信じるほとんどである。 今回落選はしたが、信号は発した。 誰が信号を、信号として受け止めてくれるだろう。 傲慢ではあるが、そのことで、日本の現代詩が問われているのである。 かなり傲慢であるけれど。 |
||||||
| 06/09/19 | 先月末、「現代詩手帖」の「現代詩新人賞」に応募した。 12年前の詩だが、その時は混乱し、うまく自己評価できなかったが、今回どれを応募しようかと見返して、けっこうよかったので応募した。 応募規定よりかなり枚数超過していたので、いくつかの詩を削った。 その結果、引き締まった連作になったと思う。 削るという作業をして、これはリミックスだなと感じた。 言葉自体は二か所をのぞいて変えなかった。 余分をカットしたという感じだ。それがリミックスと感じさせるのだろう。 詩、あるいは言葉に、不安はない。 ただ、私の詩はかなり実験的なので、それがどう受け入れられるかが心配だ。 と同時に、妥協的な選択をして応募したような気がするのも、不安材料だ。 実験的であるなら実験的である詩で勝負するべきだったのかと。 それはそれで、 自分の詩について、なんとか説明しようと、今考えている。 もちろん受賞後のインタビュウに備えてだ。 我ながら自信過剰の脳天気だが。 ところが、うまく説明がつかない。 つまり、私は言葉で何かを言いたいのではなく、言葉自体が言いたいのだ、ということを、どのように述べればいいのだろうか。 私が何を見、何を考え、何を感じ、そして何を言いたいのかということは、 私の関心の中には全くない。 もしそういったものが私の詩から読み取れるとすれば、それは私の「戦略」でしかない。 しかし、私は唯美主義者ではないようだ。 言葉と言葉の重なりや連なりの中に、私のどろどろとした収まりのつかない思いがあるのだ。 ということを、私の詩を読んでくれる人が分かってくれればいいのだけれど。 |
||||||
| 06/09/13 | 昨日は広島に残っている次男の誕生日で、妻と三人で近所の料理店に夕食に出た。 昨日から雨が降り続いているせいか、昨晩のことを思い出すとなんだか悲しい思いになる。 三人で、ソーセージの盛り合わせ、鮭のクリームときのこソテー、子羊の香草焼き、イカのトマトソース煮、ピザ二枚、スパゲティ二皿。 どれもが慎ましやかな量であったからか、味が息子が感動するほどにはもう少しだったからか、あるいはそんなわずかな料理で誕生日を祝ったからか、やはり雨のせいか、 悲しい思いがしてならない。 夜になり、雨が上がり始めると、そんな気分もなくなってきたのだが。 |
||||||
| 06/09/02 | 子猫を殺すことについてのエッセイについて、話題になっているが、 「避妊」か「子猫殺し」かが問題ではないな。 「猫」を「ゴキブリ」に置換して、果たして同じ問題になるか。 ゴキブリ殺しは問題にならないどころか、ゴキブリ殺しの薬剤がCMで流れている。 なぜゴキブリならよくて、猫ならいけないのか。 論理的な説明をしてほしい。 汚いだの可愛いだのといった感情論ではなく、 バイ菌をまき散らすとか鼠を捕るといった利害論ではなく、 「猫」と「ゴキブリ」の存在の論理的な違いはどこにあるのか。 なんてことを言ったら、猫とゴキブリをいっしょにするとんでもないやつだと、私は非難されるのだろうか。 非難されても、私の言っていることは正しいのだからしょうがない。 私は、ゴキブリが部屋に出るのが気持ち悪いのと同じくらいに、猫が自分の部屋にいることが気持ち悪い。 だから、猫もゴキブリも部屋に入らないように措置を講じている。 ゴキブリはここ20年来、部屋で見たことはない。 猫は、・・・・・・・猫とゴキブリは違うと考えている彼女が、2匹も連れ込んできたが、私の部屋にはかろうじて入れないようにしている。 てな具合に終われば、エッセイぽいのか。 |
||||||
| 06/07/20 | 翅割っててんとう虫の飛び出づる 高野素十 今日の「折々の歌」にでていた。 ひたすら自然観察に没頭した結果がこの言葉である。 言葉とは何であるか。 言葉とは人そのものであるとは、あまりに日本的な考えなのであろうか。 61年前に、私たちは、言葉に関して、何らかのものを捨て去ったのであろうか。 |
||||||
| 06/06/29 | 前項の続き、というかその例証。 仲正昌樹『「分かりやすさ」の罠-アイロニカルな批評宣言』(ちくま新書) その内容を云々するつもりはない。 云々するに価する内容か、あるいは自分に云々する力や資格があるか、わからぬ。 今、半分の手前まで読んだが、これまでの端々に、ネットへの書き込みに対する予防線がはられている。 20頁「・・・・勝手な思い込みで読み始めて、見当外れの悪口をネットに書き込まれては迷惑である---言っても無駄だとは思うが。」 21頁「・・・・などと間の抜けたことを、ネットに書き込んだりするおバカさんも・・・・」 以下各所に執拗に同様の「書き込み」がある。 「書き込み」と言ったのは、まさに活字として筆者は「書いている」からである。 本人は「文筆家」ではなく「研究者」あるいは「ネット作成者(正確には、サイト作成者、あるいはブログ作成者か?)」と思っているのかもしれないが、言葉を使って不特定多数にアクセスを試みる以上、それは(過去の概念からすれば)「文筆家」以外の何者でもない。 文筆家である以上、「言論」に対する「反論・中傷・誹謗」は、言論で対するか、さもなければ、沈黙で対するしかないはずである。 それを、「ネット」であるという理由によって、筆者は拒否しようとしている。 もう一つの例。 私の高校時代の同級生のメイリング・リストで「不適切な発言」があったために、その発言者はメイリング・リストの管理者(もちろん私の同級生、というか、友人)から「管理人の裁量で発信者をMLから削除させていただきました」ということになった。 ほぼ二日間、折にふれ考えた結果、私は何も言わずに、そのメイリング・リストから自主的に退会した。 この二例は、ネットであるがゆえの過剰反応であるように、私は思う。 これらの例は、たとえば手紙であったり、あるいは肉声による会話であれば、反論の文章を書いたり、(苦々しく思いながらも)無視したりしたであろう。 それを、二つの例に共通した反応として、ネット上の存在を消去しようとしている・した、のである。 それは、やはり > 「私」は「私」であると思っている脳が、「私の脳」も「あなたの脳も」いっしょくたになるのが、インターネットなのだ。 からとしか、考えようがない。 ネットは、自由な場であるはずである。 いや、そもそも、言説の場とは、自由であることが大前提として設定されていなければ、 それは検閲を許す、言論の場とは言えないものであるはずである。 よく考えてほしい。 日常の(たとえば)「井戸端会議」レベルの会話では、どうか。 否応なく、反論・中傷・無駄話・喧嘩の売り買い、はあるではないか。 それに対して、私たちはどう反応し、どう対処しているか。 そうした日常レベルの言説の存在が許しがたくなるのが、ネットという場なのである。 それは、(ある意味予定調和の)自分の脳内のできごとであると、私たちがネットを(論理的でなく、直感的に)理解しているからではないか。 だから、私は、個人のブログや、掲示板を持たない。 こうして不特定多数に言葉を発する以上、それはすべての誹謗中傷・反論・無駄話を許容しなければならないし、 それがいやなら、それなりの発語をする努力(つまり、文筆上の精進)をしたうえで、すべての誹謗中傷・反論・無駄話に対して、反論や無視をしなければならない。 日常会話のレベルですら、私たちはそうしているのに、ネットの場では、必要以上に防御的になるのは、 やはり、 コンピュータが脳の延長であり、ネットは「私」の脳の延長が「あなた」の脳の延長と否応なしに一緒くたにされる場であるからだ。 そもそも、この文を書いている「私」が、「私」であることを、「あなた」はどうやって確信しているのか? この文を書いている「私」はじつは「私」ではない誰かかもしれないではないか。 コンピュータ、あるいはネットにおけるアノニマス性とは、 コンピュータやネットが自分の延長であるという大前提によって保証されているのである。 |
||||||
| 06/05/25 | 祥月命日 インターネットとは何かについて。 多くの人の「印象」的理解として、 テレビと電話と手紙が、ひとつの機械でできるといったものではないだろうか。 しかしながら、機械は人間の肉体の拡張であり、コンピュータは肉体としての脳の拡張であるならば、 インターネットとは、脳と脳とがつながり、無限につながることにほかならない。 「私」と「あなた」が、便利に通信できる機械・機能ではなく、 「私」と「あなた」が、否応なく区別できなくなるシステムがインターネットなのではないか。 インターネットは魔法の杖ではない。 いまだにインターネットによって何かが変わると、楽観的に、あるいは儲けチャンス的に考えている者が(とくに私より年配者に)多いようだが、 それを単純に楽観視したり、チャンスとしてとらえることは、私にはできない。 私が、たとえば、こうしてホームページを作成するために文字を打ち込む。 そしてそれが、ネットによって流出することは、 私が他のPCにインタラプトすることであり、同時に私が他のPCからインタラプトされる場に自分をさらすということである。 総じて、過去も今も、日本語は、外来語をそのまま受け入れることによってその語の本来の意味を看過してしまう。 インターとはつながりを意味していようが、「in-t・er」と考えれば、流入・流出を相互になすことであろう。 「私」と思っていることが「あなた」であり、「あなた」と私が思っていることが「私」になるのが、実はインターネットの世界なのではないか。 「私」は「私」であると思っている脳が、「私の脳」も「あなたの脳も」いっしょくたになるのが、インターネットなのだ。 そう考えれば、2ちゃんねるから小学生の殺人事件まで、説明はつく。 自分の中に自分をインタラプトするものがあれば、それは抹消するしかない。 そしてそれは、deleteキーを押す(というより触れる)ように簡単なものとして、私たちには認識されているのだ。 人を始めとする「存在」が重いのか軽いのか。 それすら、キーボードを叩くことによって形づくられる世界の中のものになってしまったのが、今なのである。 人々はそれを知らない。 テレビと電話と手紙が、ひとつの機械でできる、それがPCでありインターネットであると単純に=印象的理解として、思っているだけなのだ。 そして私は、そうした理解が、正しいのか間違っているのか、論理的に判断できる位置に立っていない。 私もまた、そうした理解の渦の中にいて、渦に乗らなければ呼吸すらできないと思いこんでいるのである。 父が、心不全(的症状)で入院している。 私も脊椎までの疲労感を、滲み出すように感じ始めている。 今夜は母が死んで初めて、自宅で夕食を摂った。 楽である。正直に言う。 |
||||||
| 06/01/01 | 初七日、弟のせきあえぬ涙に 寒夜涙(かんやなみだ)凍れる夜の帰り路 嫂(あによめの)思ひは流しに今日ぞ泣く |
||||||
| 05/12/25 | 母死に給ひける夜 消え残る雪も軒端の寒月夜(かんづくよ) |
||||||
| 05/12/17 | 寒波の来ける日、死に近き母の枕辺に枯れ野をもとめて 枯れ草にまだ緑ある冬野かな 前項の訂正。 母の眼はいまだ白濁せざりき。 |
||||||
| 05/12/15 | リモコンでチャンネルを変えるように、サイトを行き来する。 いわゆるネットサーフ、とも少し違うのは、「お気に入り」をクリックするから。 母が死にそうだ。 「比喩」とか、「表現」とかでなく。彼女の肉体が、死と闘っている。 意識はもうない。 意識の有無とは、このように、簡易に他者にゆだねられているものなのか。 私は彼女が確かに私を見たと思っている。あるいは思いたがっている。 白濁しかかった角膜を通して、光学的刺激が脳に何をもたらしたのか。 私は、確かに彼女は私を見たと「思いたがって」いる。 「思いたがっている」ことを超越して、彼女は私を見たかもしれないし、たんなる「光学的反応」として生体反応を示しているだけなのかもしれない。 しかしその反応は、私に確実な反応をもたらしている。 人が人をとらえることは、このように難しいことである。と同時に、 容易に「真実」に私たちを導くものであるのかもしれないように思える。 「音楽」は「決めつけられた音」を行き来すること。なのだろうか。 母は、今、懸命に生きようとしている。 ほっといても生きようとするのが、私たちの本質である。 私はそのことを十代の時に、思った。 母はそれをいま実証している。 「意識」とはなにか。「意識」があるから私たちは生きているのではない。 また、生きているから「意識」があるのでもないのだろう。 しかし、母は生きている。生きようとしている。 私たちが「お気に入り」をクリックするとき、そのクリックするという行動の意味は、 私たちの「生の本能」とでもいうべき肉体と、どれほど関係しあっているのだろうか。 もう一度そのことを確かめるために私は彼女の手を握り、彼女は私の手をかすかに握りかえした。 言葉は生者のものであり、それがどれだけ死者と、あるいは死にゆく者と交叉するのだろうか。 |
||||||
| 05/11/22 | 昨夜の夢のこと。 大学の文化祭(だったように思うが、そんな経験はなく、そうだと思っただけ)で、本番はいつまでもこずに、楽屋として割り当てられた教室(なぜか畳敷きだったが)で、仲間(とは言っても職場の同僚たちばっかりだったが)とぐだぐだしていた。 先出のバンドの方々(これはフォークのライブでの出演メンバー)がステージに出て行くのに挨拶したりして。 なにかの拍子に文学の話になって、 現代文学は小説の時代で、 それでは近代文学はというと、詩の時代だ と私が言うと、仲間(とは言っても職場の同僚たちばっかりだったが)が興味を示したので、黒板のある部屋へ移動して説明を続けた。 その後シーンは元の部屋へ戻り、出番がなかなか来ないままエビや魚の天ぷらが次々に持ってこられて、カレイの天ぷらが何枚も、まるで扇のように持ってこられたのを、私も数枚もらって、小さめのを頭からかじって骨ごと食べた。 それはそれでいいのだが、 現代文学は小説の時代で、 近代文学は、詩の時代。 というのが気になる。 夢の中の説明では・・・・・・現代文学についてはよく思い出せないが、 近代文学は、新しい言語を開発していったという意味で、詩の時代だと説明した。 夢でありながら、なんだか正しそうで、気になる。 もうちょっと考える価値はあるかもしれない。 |
||||||
| 05/11/19 | NHKスペシャル 「高倉健が出会った中国」の中で、中国の青年が言っていた。 農業は底辺に位置すると。 そこにはもはや、底辺であるからこそ人々の生を支えるという誇りも使命感もない。 農業は産業化され、どれだけの経済効果があるかないかという計算のうちにしか存在できなくなっている。 このことは、農業が起こったときから農業がはらんでいた問題なのだと思う。 農業は、一人当たりの生産高で一人以上の人口を養うことができる。 余剰人工は、遊んでいても食えるという計算である。 日本でも、工業化、高度経済成長を推進したのは、農業地域からあぶれた、すなわち耕作せずに食える人口であった。 そして、農耕人口が養える非農耕人口が農耕人口を超えたとき、逆転が起こった。 非農耕従事者が、価値観的に優位に立ったのである。 あくまでも価値観的にである。 ここにも、近代的二元論と同じ位相が見て取れるのではないか。 農業が養うものは、人間の肉体である。 常に肉体を魂の下位に置いてきた二元論が、ここにもあるのではないか。 そして、農業が人間の「叡知」の原初的位置にあるならば、現在いわゆる先進国で起こっているこの現象は、農業がその始原からはらんでいたものなのであろう。 現在のいわゆる先進国とは、ヨーロッパ的キリスト教観念によって「先進」と位置づけられているにすぎないからである。 たぶん、産業としての農業が、私たち非農耕人口を養っていくであろう。 そのことが破綻したとしても、人口が激減するだけですむ。 そのことは、皮肉でも当てつけでもなく、ただそれだけのことなのである。 |
||||||
| 05/10/11 | 10月4日、沖縄平和祈念公園の「平和の礎(いしじ)」を訪れた。 23,9092名の沖縄戦戦没者の名が刻まれている。 初めての訪問ではなかったが、今回、礎を前にして、歯がみ足を鳴らしたくなる悔しさを感じた。 これだけの人間が、小さな沖縄で恐怖と憎悪を持って出会わなければならなかった。 死して後こうして並んでも、なんにもならないではないか。 50万あまりのアメリカ軍兵士と、11万あまりの日本軍兵士、そして沖縄の人々。 平和な今出会っていれば、どれほど幸福な出会いであったろうかと、「愛・地球博」の盛況を見て思う。 |
||||||
| 05/10/07 | 広島から沖縄を考えてみる。そのシリーズの最初。 文化は固定的なものでなく、その時間経過によって変化しつづけるものであるので、固定的な物言いは避けねばならないが、今回沖縄に行ってみて考えたことを。 沖縄の文化は、非洗練的に見えるものが実は洗練されたものであるのだが、それは、どうしてなのか。 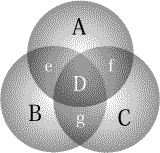 DはA、B、Cの周縁に位置しているが、それぞれの周縁であるe、f、gに対しては中心をなしている。 沖縄はアメリカ、日本、中国の周縁に位置していながら、それゆえに「周縁の中心」ともいうべき位置をなしているのではないか。 沖縄が一見して洗練と非洗練との間を行き来しているように見えるのは、私が「周縁の周縁」に位置しているからなのではないか。 たとえば、「ちんすこう」や「サーターアンダギー」、「ゴーヤチャンプルー」、「フイリチー」といった食べ物は、私からすれば洗練されたものには見えない。 それは、「道楽屋」の和菓子やあるいは××製菓の箱菓子、シャルパンティエのクッキーと比べてのことで、そのことはじつは私がそうした文化の周縁にいることの証明になっているのである。 上の図を、便宜上Aをアメリカ、Bを日本、Cを中国とすれば、私はeやgにもいるのではなく、eやgに比較的近いBにいることになるだろう。 それゆえにかえって、AあるいはBが気になる位置におり、そしてDはBの範疇に入るがゆえに気にならないのである。 沖縄は上図のDである。 Bの目から沖縄に触れたとき、それは非洗練に見えたのだが、じつは高度に洗練されたものであった。 それは、それぞれの土地にそれぞれの文化があるといった文化の独自性論ではなく、 首里城に展示してあった龍の螺鈿細工の盆の精緻さと美しさ、さらには、おそらく太平洋戦争後に起こったであろう琉球ガラス細工や、スパム料理に対する沖縄の人々の屈託のなさが創り出した洗練であるのかもしれない。 この論、まだ上手くまとまらない。読む人によっては違和感や嫌悪感を抱くかもしれないが、とりあえずのメモとして。 |
||||||
| 05/09/20 | 2005年9月18日(日曜日)付中国新聞32面 「小銃抱えて商店行進佐世保陸自」(他の報道機関) 同日同紙33面 「超音速/旧海軍料理はハイカラ」 衆議院選挙で自由民主党が「圧勝」し、民主党が惨敗した。 民主党の代表に前原誠司が当選し、日本国憲法第9条(とくにその第2項)の改訂の意志を表明した。 中国新聞が広島の地方紙でありながら、陸自の行進に対しては単なる報道に終わり、旧海軍にはノスタルジーを表明するという、撞着というより本性を現したという批判は、ともかくのこととしてせずにおく。 自由民主党の圧勝は、小泉純一郎への賛意であることにはちがいないだろうが、郵政民営化論議で特に顕著になった小泉の物の言い方が気になっていた。 議論を斜めに流し、レトリックのみで説得というより頷きというに近い賛意を得る方法は、アメリカのブッシュと共通するものでもあるかもしれないが、ブッシュより東条英機に近いのではないかという気がしていた。 それで半藤一利「ドキュメント太平洋戦争への道 「昭和史の転回点」はどこにあったか」を再読してみたが、やはり言説の等質感を感じてしまう。 そして新民主党代表前原の改憲意見。 自由民主党がなせなかった消費税の導入を、アンチ自民党に見せかけた日本新党細川護熙内閣がいとも簡単にやってのけた出来レースからすれば、その天麩羅ぶりは稚拙であるが、日本という国がそちらへ行こうとしているのは明らかである。 ひょっとすると日本共産党志位和夫委員長も、乗ってはいないにせよ体を張って止める気配を感じさせない。(いや、その時が来ればするのかもしれないが、結果は言わずもがなであろう) 私は、日本国が合法的軍隊を持つことへの危機感を本能的に持っている。 それは大塚英志が言う戦後民主主義の落とし子で、自虐史観が脊髄に染みついているからかもしれない。 その一方で、日本国が正当に軍隊を持つことをも、考えている。 日本国憲法第9条に記された戦争の放棄及び戦力の放棄は、じつのところ日米安全保障条約とセットになっている。 日本国は軍隊を持ってはいけない、そのかわりアメリカが日本を軍事的に防衛する、というセットメニューである。 もちろん、アメリカが日本国を軍事的に防衛するとは、日本国がアメリカの一部=防波堤という前提で成り立つ。 アメリカはアメリカのために、日本国を防衛すると言っているのである。 日本国が独立主権国家として成り立っていくのなら、在日米軍をすべて撤退させなければならないはずであるが、もし日本国が、アメリカの思惑とは違う進路をとろうとすれば、すべての在日アメリカ軍施設の撤去と、51655人の在日アメリカ軍軍人と53908人の関係者を退去並びに解雇せねばならず、その前に51655人の在日アメリカ軍が、軍事的行動によって日本国を制圧するのに数日もかからないだろう。 これだけの外国の軍隊が駐留していて、独立主権国家と言えるのだろうか。 しかし、改憲議論は日米安全保障条約(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約)に向かおうとはしていない。 アメリカは不景気を打開するためにアフガニスタン、イラクに戦争を仕掛け、アメリカの不景気を少しでも軽減するために日本は軍事力を法制化しようとする。 これが改憲議論の正体だと思う。 いまだに他国によって軍事的に制圧されている国家が、国際連合で理事国になろうとしているのであれば、国際連合が大国の顔色次第であるのは言うまでもないことになる。 ん〜、かなり過激なことを言っている? 理屈でものを言えばこうなるんだけどなあ・・・ 日本人は見たくないものは見ないというか、見えないものとするという特性(あるいは特技)が古来よりある(のだろうか?)。 |
||||||
| 05/09/18 | NHK総合テレビの7時のニュースを見ていると、科学者の描く未来像というのを、想像図入りで流していた。 空中を車が飛び、ビルディングが並んでいる。 いっしょに見ていた彼女と、(いわゆる)「科学者」の想像力の貧困さに嘆いた。 科学的発達を捨てた未来像というのを、科学者は描けない。 当たり前と言えば当たり前だが、自分の今いる場所を飛び抜ける想像力がないというか、いや、度胸の問題だな。 |
||||||
| 05/08/27 | 「ヨーヨー・マとシルクロード・アンサンブルの仲間たち 〜対話と創造の8日間〜」(再放送)を見たが、どうもシルクロードとか、大陸西方には興味がわかない。 南洋からの海の路の方が、夢や想像をかき立てる。 自分のルーツがそちら方面にあるからなのだろうか? あるいはそう思っているからだろうか。 おたく文化とかが日本を代表する文化になっているようだが、あれは東京文化だな。 広島には、ああいうのないもん。 歌舞伎もない。文壇もない。 ないから遅れているとかいう問題ではなくて、ないのが文化。 いや、それは正確な言い方ではない。 他の文化があるのだよ。何かと言われると少し困るけど。 たとえばいつかシライシさんが言ってたけど、「原爆-平和」というのも、じつは広島の文化を担っている。 沖縄にはいったいいくつ台風が上陸しているのだろう。 本土では上陸すると必ず7時台のニュースになるのだが、沖縄には上陸しているのだろうか。 メディアの計量・経済主義がここにも表れている。 少数の住人しかいない場所のことは、よほどの惨事でないとニュースに載らない。 いくらメディアの正義を言ったところで、思いやりという名の想像力のない正義はファシストと同じだと思う。 ・・・・・・どうファシストなのかと聞かれても困るけど。 そろそろ今の仕事を辞めて、したいことしたい。 東京で暮らしてみたい。 そうすると詩も変わるだろうか。 私の詩が流通する詩だとは思わないが、東京で変わるとすると、流通の可能性もあるのではないかと、夢想してしまう。 まあ、3人に読まれれば御の字だが。 そういえば、京都で4年、東京で3年、あとは新潟の漁村で暮らすという算段をしていたことがあった。 今の彼女もついてくるのだろうか・・・ それはそれでいいのだけど、どうやって食っていくかということが先ず気になって、仕事を辞めることができないというドツボにいつもはまってしまうが、キップルに埋まっている自室を眺めると、どうでもいい気にもなってくる。 |
||||||
| 05/08/08 | 平和記念資料館で仕事があった。 レストハウス「あおぎり」の喫煙場で煙草を吸おうと取り出すと、コーカソイド系の男性が簡易型ライターを取り出して点けてくれた。 ありがとう と日本語で感謝して、少しして英語で話しかけた。 訊くとドイツから来たと日本語で言うので、日本語できるかと言うとそれほどでもと言うので英語で話した。 ドイツ平和村の関係で来たらしい。今回2回目だという。 私の母が被爆者だと話し、彼はまだ放射能はあるのかと問う。 詳しい数値を上げて話そうと思うが、知らない。 適当な言い方で終わってしまった。 休憩の時間も終わり、see you again と言って分かれた。 自分が何も勉強していないことに、がっかりした。 体験だけでなく、科学的な検証も継承していく必要があると感じる。 明日は沖縄に行くと言っていた。 沖縄もまた平和について重要な場所だと言うと、そうだとうなずいていた。 彼はまた来るだろうか。 ぜひもう一度会いたい。 平和について考えているのは、私たちだけではなかった。 そんなあたりまえのことを、ほんの煙草一服の間に経験した。 残留放射能について 残留放射能について 残留放射能について 残留放射能について 残留放射能について |
||||||
| 05/07/25 | 夏草を刈る ゴキブリを喰らうゴキブリ |
||||||
| 05/06/21 | 最近なんだか、こうした↓評論めいた文章を書く気分でない。 「死者と交わる言葉」と題して、詩集を書いている。 そっちの方が、気分的に合っている。 |
||||||
| 05/06/07 | 80年代の「記号論」や「意味論」はどうなったのだろう。 トーキング・ヘッズの「Stop Making Sense」が85年。 なぜあの頃、「記号論」や「意味論」が盛んだったのだろうか。 そして今、「記号論」や「意味論」はどうなったのだろうか。 あの頃を「大人」あるいは「大人になったばかり」として生きた者として、まとめておかなければいけない。 まあ、「いけない」というのは自分にとってということだが。 |
||||||
| 05/05/29 | たかだか「TVタックル」にオブジェクションもないのだが、 日本人のモラルのモデルを、幕末や明治に求めるのはやめよう。 たしかに、日本人のモラルの理想型がそこにあると考える心理はわかる。 しかし、そのモラルが、どのように形成されたか考えることなしに、いわば盲目的に昔はよかったと言うことは、やめよう。 単純な話である。 戦国時代と、戦国時代を引きずった安土桃山時代に、なんとか終焉をもたらそうとしたのが初期徳川幕府の意向であり、 それが規範となって前例を破ることを極端に嫌った性向が形作られたのが江戸時代のモラルとなっていったのである。 さらに、それまで『無知蒙昧であった』武士以外の階級を、兵士として自覚させる核になったのが、上記の武士のモラルなのである。 モラルが『モラル』として独り歩きし、そうした「習慣」の本来の意義を忘れたところに、私たちの「モラル」がある。 日本男児が短髪になったのはたかだか百何年か前からなのに、もはや長髪はフォーマルの地位を追い落とされているのである。 |
||||||
| 05/05/14 | 大塚英志が違和感として表明している「私」の希薄感について。 インターネットの普及によるとすれば、私がこれまでに書いてきた「PCは脳の延長である」論で片付く。 道具が肉体の延長であるとすれば、PCは肉体としての脳の延長である。 そしてそれは「自分の肉体」の延長であるとすれば、たとえば大塚英志が求めているような「他者に対しての私」「他者と対峙する中に存在する私」は、現れようがない。 全てがベタな一面の中にあるだけである。 では、それは、PCあるいはインターネットによってもたらされたものなのか。 そうした性格を持つPCあるいはインターネットを受け入れていった、その大元にあるものは何なのか。 05/05/03の項に書いた、ディジタル以前にディジタル・ミュージックが存在していた80年代、ということになるのだろうか。 PCやインターネットの匿名性が議論されるより前に、私たちは匿名性を望んでいなかったのか? なぜ私たちは匿名性を望んだのだろう? PCやインターネットは道具に過ぎず、それを選んだということは、私たちの中に確実な願望があったということであり、それはいったい何なんだろう。 ひとつのキーワードは、表現の製品化のような気がしている。 経済主義(経済至上主義)化の中で、それがなされていったのではないだろうか。 と、ひとまずは自分の議論に持っていっておく。 消費することが正義であり、消費する者だけが正義を実現しうる。 そうした中で、「私」はどういうありようをとげたのだろうか。 |
||||||
| 05/05/12 | 何年ぶりだろうか、中島敦の『山月記』を読んでいる。 以前は「虎」が象徴する思いのあり方に気が引かれていた。 中島敦自身は虎になりたかったのではないか、しかし自分の中にある、羞恥心による臆病さや、妻子のことが、彼が文学に向かう抵抗となっていたのではないか。 「李徴」はあこがれであり、自らを虎に変えてでも、文学に専心したかったのではないか、と考えていた。 今の読みはこうだ。 「李徴」は「虎」なんかになってはいない。 じつのところ彼はホームレスなのである。 思わず人前に姿を現したホームレスの「李徴」が、それが親友の「袁さん」であったがために、叢に身を隠したのではないか。 そして自らを「虎」に身を変えたといつわった。 もちろん「李徴」は姿を見られたことはわかって、そう言っているのである。 「袁さん」もまた、その「李徴」の心情を痛いほど理解したので、話を合わせている。 「李徴」が虎になったかどうかは問題ではない。 それは「袁さん」たちとは違う身の上になったというだけのことだ。 身をやつしたものの痛切な思いが述べられ、またそれを黙って聞いている親友の痛い思いがある。 最後のシーンで「李徴」は虎となったわが身を親友の前にさらすが、それはじつは身をやつした人間である「李徴」の姿である。 それを「袁さん」は、「李徴」の言うとおりに、「虎」だと見たのである。 観客として見れば滑稽なシーンであるが、二人の心情・真情から見れば、痛切なシーンとなるだろう。 今の私は、そういうふうに『山月記』を読んでいる。 それはたぶん今の自分の真情であろうし、そういった読みもまた、中島敦の真情にいくばくかは近づいた読みなのではないかと思っている。 中島敦は三十三歳で死んだ。 私はそれよりさらにひとまわり以上生きのびている。 彼の思いの痛切さ、その痛切さの生々しさが、ようやく理解できるようになったのだろうか。 それとも、まだまだなのか。 |
||||||
一日飛びの4連休。全部ドライブ。1日は雨だがあとはフルオープン 5月1日日曜日 「紺屋」のラーメンとチャーシュー飯 「香木の森」 「広島屋」のパンプキンパン。椎茸のソテー 5月3日火曜日 「休日の家」のコーヒー 「イマージュ」のプリンとフルーツケーキ。「あじ安」の焼き肉、オジンスープ。 5月4日水曜日 尾道、「YOU-YOU」の水出しコーヒーとワラビモチ、 「桂馬」の蒲鉾。たこ入りいなり寿司 5月5日木曜日 弥栄ダム。たこ焼き そば、「おんぼろどうふ」、わさびの醤油漬け。 |
|||||||
大塚英志が自分はITからは距離をとっているというようなことを書いていることから、自分がPCで詩を書き始めたときの違和感を思い出した。 |
|||||||
| 05/05/03 | > その間隙を縫うように登場したテクノ・ポップはじつは、現在にまで続く、そしてこれから > も続いていくであろう、「サンプリングの時代」の幕を開いたのではなかったか。 > > 「サンプリングの時代」とは、全てが同じ平面上に並んでいると感得される時代である > 。 > それと軌を一にしてCDの時代が始まった。 実際には、YMOのアルバムは全てアナログ盤として発表された。 テクノは、アナログ時代の最後であった。 しかしながら、人間が機械のふりをする、あるいは、不完全な機械に完全な機械のふりをさせる、のが、テクノであり、それゆえに、 次代を導きだしたと同時に、 次代についていけなかったのである。 |
||||||
| 05/04/28 | > 昔のことを思い出して、胸苦しくなることがある。 > なにか大事なこと、楽しかったことがあったはずなのに、思い出せない。 (04/09/29) 大塚英志の『戦後民主主義のリハビリテーション』読んでいて、 彼が80年代をきっちりと記憶し、把握していることから、もう一度上記を思っている。 80年代に私は何を考え、してきたのかと。 大塚は自身を「おたく」であり「新人類」の一員だと規定しているが、同じ年の生まれの私はしかし、それらは自分のあとの世代だと認識している。 それは私が「遅生まれ」の「早行き」だからなのかもしれない。 私は前世代の一番尻尾にいるという意識は、就職して間もなくから持っているのは確かだ。 前世代になんとなくの異議を唱えながら、後世代に対しては仲間・同族意識を持てないというか。 それらはともかく、自分の仕事がらか、時代の流れとは距離のある生き方をしてきたのだろうと思う。 冒頭の胸苦しさは、たとえば大塚が書いているような時代意識・認識から離れた生活をしてきたことなのかもしれない。 あるいは東京と広島という、距離=時間=時代のラグなのかもしれないとも思ったりしている。 自分にとっての80年代とは何かというと、規範・模範を見失った時である。 というか、自分が本格的に自分の表現というものを見つめ始めた時であるのだが。 ジャズの本流であるかのように見えたフュージョンが簡便なイージー・リスニングへとスライドし、そうでないものはロックの表現とジャズの表現との狭間で、そしてそのロックやジャズ自身も、自らの根拠を見失っていったのが、80年代であり、 その間隙を縫うように登場したテクノ・ポップはじつは、現在にまで続く、そしてこれからも続いていくであろう、「サンプリングの時代」の幕を開いたのではなかったか。 「サンプリングの時代」とは、全てが同じ平面上に並んでいると感得される時代である。 それと軌を一にしてCDの時代が始まった。 ディジタルの時代とは、コピーによる劣化のない時代であり、経年変化のない時代である。 テクノロジーによって、過去も現在も同じ平面上に並ぶことができるようになったのが80年代であり、その時「おたく」や「新人類」が登場したというのは、必然であったように思える。 その時以来、私たちは何も新しいものは生み出していないのではないか。 ただ、そこにあるものに対する意味づけが少しずつ変化しているだけなのではないか。 |
||||||
| 05/04/10 | 今日は彼女と廿日市市の図書館へ行って、『文學会』を読んだ。 高橋源一郎と関川夏央の文章が面白かった。 高橋源一郎は、小説において死がどう表現されているかという論点を切実に叙述していて、興味深い。 が、 私の命題は、 言葉が、死んだ者たちと交叉する場所、なのである。 我ながら困った命題を設定した感もあるが、自ら設定したということは、何らかの解答が得られる予感があるからなのだろう。いや、そうに違いない。 文学が死をどう表現したか、は答えやすい問いだ。 いや、それすら高橋源一郎の論考の対象になるほどに複雑なものを持っているのだが、 私が設定した命題はどうか。 死んだ者たちとは何か。 交叉するとは、どういう現象か。 そういったことに、明確に答える何かを、とりあえず私は持っていない。 そこから考え始めるしかない。 ありゃりゃんこりゃりゃん、なのだけれど。 言葉が、死をどう描いたか、でいいのだろうか。 あるいは、言葉によって死がどう語られたか、でいいのだろうか。 つまり、言葉とは何か、ということに答えることから始めねばならないのだろうか。 私は、誰が、死を、どう、言葉で描いたか、ではない、 言葉そのものが、死と、どう、かかわってきたか、を考えようとしているのだろうか。 そんな気がする。 |
||||||
| 05/04/07 | 言葉が、死んだ者たちと交叉する場所はどこだろう。 死や死んだ者たちを表す言葉は、ある。たとえば『こころ』の「三.先生の遺書」のように。あるいは、『少女架刑』のように。 死んだ者たちと交叉する言葉は、どのようなものなのだろう。 死や死んだ者たちを表す言葉を見つめることで、わかるのだろうか。 『古事記』『日本書紀』や歌集、日記や物語文、随筆、それらを読み漁ってみようか。 何かが見えるかもしれないから。 |
||||||
| 05/04/05 | 『私たちは生きているか』というのは、じつは『・・・か』に意味がある。 いや、それは誰かにとってというのではなく、私にとって。 簡単に言えば、保留なのだ。 私は生きていると、確認したいのであるが、その確認はどこにあるのか。 あるいは生きていることを実感しているのだが、その実感を定置できないでいる。 どうもふらふらしているし、ふらふらしていることで安心しているフシもある。 ひょっとしたらその『・・・か』に何者かが入り込む余地があるのかもしれないとも思っている。 そこが死んだ者たちと生きている者たちとの交叉するところなのかもしれない。のだが。 |
||||||
| 05/04/01 | 昨日の考えを記しておく。 私たちの物理的存在、つまり、肉体には今・現在しかないのではないか。 過去は記憶という意識の中にあり、 未来は予測という意識の中にある。 私たちを存在させている肉体は、その一つ一つの細胞は、今・現在、存在するためにつねに、たとえば新陳代謝という言葉のように、変化をしつづけている。 そして、私たちの意識というものは、まるで現在を肉体に任せているかのように、過去という記憶と、未来という予測ばかりを気にしている。 自分の現在を認識するためには、肉体と対話するしかないように思う。 ヨガのように肉体を隷属するのでも、ユダヤ教・キリスト教的に肉体を下位に置くのでもなく、意識にとっての他者として。 私たちは、何千年もの蓄積の上に、「肉体vs意識」観を作り上げているのだろうか。 それとも意識は、肉体から独立しようとしているのだろうか。 「意識」とこの項で私が呼んでいるものの定義付けは、どうなるのか。 どうなるか、って言ったって、自分でせねばならないのだけど。 今日は、養老孟司の言い方をなんとなく避けてみたが、それは、 脳も肉体の一部であるからして、脳vs肉体というのもすっきりしないと思ったから。 「ワニの脳vsヒトの脳」という言い方もある。 まあ、脳だって肉体であるし、その証拠に損傷したり、あるいは酸素や栄養素が供給されなければ存在できないわけだし。 またしかし、私たちは永遠の存在を信じている・信じたがっているわけだし。 その信じたがりが、過去という記憶や予測という未来を創りあげているのだと思う。 猫(べつに猫でなくてもいいので、動物)にとっての過去は肉体に刻まれ、肉体に刻まれた過去が未来を予測させているように思える。 私が猫(べつに猫でなくてもいいので、動物)を尊敬する(=真似しようとしている)のは、その点だな。 ヒトの脳は重すぎるのか? だろうか? |
||||||
| 05/03/30 | 「冒険CHEERS」が終了した。 初めて見たのは、萩へひとり旅した旅館でだった。確か、太陽熱で料理を作るというのを、山と海とでやっていた。 なぜか心惹かれた。 なぜ? 子供っぽい冒険心をくすぐったから? あるいは、こんなこともありだよな、っていう「小ネタ」ぽい、題材? 「鉄腕dash」の子供バージョンではあったが、いつまでもある小さな好奇心を刺激してくれる、いい番組だった。 もちろん、「やらせ」は前提だが、その前提なしの番組が成り立つのかどうか、今の日本では大いに「????」だが。 |
||||||
| 05/03/18 | 昨日の続き、というか、考え直し、というか。それともう一つ、書いておきたい。 私の新しい詩集は、 > 生きることが交差する風景を私は詩にした とはいうものの、孤独な自分がいるだけのような気がするし、 そうでなく、そういう自分が他者を求めていたり、他者とすれ違っていたりする詩なのかもしれない。 そうした、なんだか孤独な自分が他者とすれ違う瞬間と言えば、そうなのかもしれない。 であればそうした、なんだか孤独な自分が死んだ者たちとすれ違う瞬間も、見えるかもしれない。 もうひとつ。 私はIT状況に否定的な立場であろうとしているが、じっさいはどっぷりIT状況にひたっている。 ひたっているからこそ否定的、と言えば言えるのだが、なぜ否定的スタンスをとろうとしているのだろうか? 人間は、自身の延長として道具を作り出してきた。 IT環境がこれまでの道具と違うところと言えば、IT環境は人間の意識の延長としての道具だということ。 コンピュータがあつかうのが、文字と画像と音であるということから、簡単に説明のつくことだ。 別の言い方をすれば、私たちは、文字と画像と音でもって生きていることを確認しているということなのかもしれない。 でもね、こんなところを見ると、だからといって一概に切り捨てる気もしない。 だって自分がこうしてネット上に文章を書いたり、HTMLで詩集を作っていたりするし。 もう少し、あるいはもっと、自分の皮膚5cm上から以内のところを、考えてみたい気がする。 さらにもうひとつ。 これもこれまで私がこの日記で言ってきたことだけど。世代論的思考は、もうやめた方がいいと思う。 今TVを見ていると、80歳の男性が73歳の妻を殺害した理由が、おかずの品数が多すぎることでの口論だという。 その前には、22歳の男性が21歳の交際相手の女性を殺害したという報道を流していた。 世代論に頼って自分の居場所を確定しようとするから、わけがわからなくなるのだ。 世代論って、けっきょく差別の構造と同じわけで、ものごとが見えなくなる根本がそこにある。 だから「若者を見直した」みたいな言辞が登場するわけで、若者はいつの世でも頼れるのであるよ。 |
||||||
| 05/03/17 | 私たちが生きるということは、死者を置き去りにすることだと思う。 慰霊 鎮魂 いかように言おうとも、死んだ者たちは私たちから絶望的に遠く離されていく。 沖田先生の著作の影響で、こんなふうな考えが浮かぶのかもしれない。 私たちから絶望的に遠く離されていく者たちは、また、死者と同じ、あるいは死んだ者として扱われる。 死んだ者たちと、生きている者たちが交差する点はあるのだろうか。 あるとすればどういう風景として、私たちにあらわれるのだろうか。 ひどく不十分な形であり、理解されにくい形ではあるが、生きることが交差する風景を私は詩にした(つもりである)。 生と死、ではなく、生きている者たちと死んだ者たち、が交差する瞬間が、次の私の詩のテーマになるのだろうか。 いや、もう少し、生きている者たちの交差を見なくてはいけないという思いも強い。 「死者のことは死者にまかせよ」と、イエスは二千年前に言った。 イエスには死んだ者たちと生きている者たちの交差が見えていたようにも、何となく思うのだが。 それはそれとして。 |
||||||
| 05/03/12 | 児のかいもちするに空寝したる事[宇治拾遺集巻一・一二] これも今は昔、比叡(ひえ)の山に児(ちご)ありけり。僧たち宵(よひ)のつれづれに、{いざ掻餅(かいもちひ)せん」といひけるを、この児心寄せに聞きけり。「さりとて、し出(いだ)さんを待ちて寝ざらんもわろかりなん」と思ひて、片方(かたかた)に寄りて、寝たる由(よし)にて出(い)で来(く)るを待ちけるに、すでにし出(いだ)したるさまにて、ひしめき合ひたり。 |
||||||
| 05/03/11 | ライブドアが提訴していたフジテレビへの新株予約権発行の差し止めを求めた仮処分申請が、東京地裁(鹿子木康裁判長)は、商法が禁止する「著しく不公正な発行」にあたるとして、発行差し止めを命じる仮処分決定した。 それはそれで、どうでもいいと言えばどうでもいいことだが。 今日の考えをまとめておく。 意識というのは、肉体に属するのではないか。 意識というのは認識であり、認識とは脳やその他の機関によるものであろう。 人間はこれまで、「意識」と「魂」を混同してきたのではないか。 「私」が「聴いている」音楽、「見ている」絵画、などなど、「私」という意識は、感覚受容器を束ねているものではないか。 そしてそれは、感覚受容器の全てが失われたときに、どうなるのだろうか。 「束ねる」というのも機能の一つだとすれば、意識もまた失われるのではないか。 私たちが死を恐れるのは、脳が脳自身が失われることを恐れているという考え方が成り立つ。 つまり、私たちの死への恐怖こそが、私たちの意識も機能のひとつであり、感覚受容器、すなわち肉体に属していることの証左と言えるのではないか。 アフリカ系アメリカ人は、「Body And Soul」と言う。 ・・・・たぶん私の経験から言うと、「Mind」と言い出したのは、Erath,Wind & Fireではないかと思うのだが・・・・ 肉体と、その肉体を離れた魂。 彼らに所有が許されたのは、その二つだけであるという、厳酷な現実と歴史があるのだが。 魂とは、肉体とは別のところにあるとすれば、それは個人の意識であるはずはなく、 また、死して後にも私たちが生きているときと同じように物事を見たり考えたり出来るその根拠として、魂があるのではない。 私たちに意識をあらしめている「物体」が存在すること自体が、「Soul」、「魂」なのではないか。 私が、現代音楽とアフリカ系音楽を同列に好んで聴くというのは、その音を作り出すという肉体の作用の中に(脳も肉体のうちという分別であるが)、物が存在するという「魂」「Soul」を、その肉体的痕跡の内に聴いているからなのだろう。 ライブドアが目指す放送メディアとネットメディアの融合が何を意味するのか、それは一目瞭然ではないか。 私たち人間は、つねに肉体の限界を求めてきた。 そうでなければ、自分が動ける以上の速度で移動することに快感を感じたり求めたりはしなかっただろうし、料理にしてもこのような複雑な味を求めはしなかっただろう。 己が肉体の限界内で移動し、肉体の損耗分を補うこと以上の意味を食餌に求めはしなかっただろう。 ライブドアは、旧式であるがゆえに肉体的メディアであるラジオと、(これまでの意味での)意識の領域により近いネットメディアを混交しようとしているのであろう。 それは、PCに頼っているネットメディアのもどかしさと限界を、堀江社長は切実に感じているからだろう。 私たちは、じっさいのところ、「他者」の存在を必要としている。 ネットメディアの中では「他者」は希薄なのである。 プッシュ型とかプル型とか言うが、そのどちらもが私たちの実際の存在とは懸け離れている。 そのバランスをとるために、旧来の肉体依存型メディアが必要なのだと思う。 これから行き着く先のメディアとしては、その両者を利用するだけで足りるはずもないのは明確だ。 しかし、融合・混交を試みることしか、今にはない。 堀江社長がドン・キホーテであるというのは、その意味においてである。 肉体の存在が自分であるという旧い認識と、意識が自分であるという比較的新しい認識が、裁判所の判断を待ったというのが今回の出来事なのかもしれない。 そしてその先に、意識もまた肉体に属するという認識が待っている。 と私は思いたいのだが。 人間が新しいことを始める動機は「快感」しかないと思うのだが。 そして「快感」は私たち人間の存在の根底を提示してくれると、思っているのだが。 |
||||||
| 05/03/08 | 先週の金曜日、沖田泰弘先生を囲んで、重松純、矢野一郎両氏と、沖田先生の出版記念の飲み会を持った。 「はまもと」で腹拵えをして、重松氏お薦めの、シングルモルトを飲ませてくれる店へ行った。 自称「沖田塾」の面々は、早く沖田先生の著述をもとに話をしたかった。 重松氏なんかは、職場での休憩時間でも私に話題を振ってきたくらいだ。 その休憩時間での話を、ゆったりとしたソファでシングルモルト(私が飲んだのは、アイリッシュを中心に三杯)のグラスをかたむけながら再現した。 それは、私が20数年間考えてきた、言葉とは何かということ。 私は二十代の半ばから、その問題に片を付けなければ詩が書けないと思っていたので、ずっと考えてきて、言葉とは形象あるいは音声で成りたち、しかし実はそのどちらもが言葉の実態ではなく、かといってその二つをなくしては言葉は存在しない。といったことを、語った。 重松氏からは、私に「言語肉体派」という尊称をつけていただき、大学時代に私の詩のファンだという藤村猛君の母君から「まあ、頑丈そうな体ね」と言われたことを思い出したりしていた。 言葉にとって、形象も音声も不可欠のものでありながら、それらは実体ではない。 でありながら、人を感動させる言葉があり傷つける言葉がある。 言葉は、それを受けとめる人間を規定し繋ぎ止め、また発する人間をも規定し繋ぎ止める。 というところまで話をした。 では言葉の実体は何か、あるいは、どこにあるのだろうか。 その後私は自分のしゃべったことに同席の面々が納得の表情を浮かべてくれたことに、安堵と満足を感じたのだが、昨日になって、じつに皮相なことしか語っていなかったことに気づいた。 あんな説明で、小林秀雄があれほど迂回路をたどりながら辿り着いたか着けなかったか確信の持てなかった問題に、中原中也が自らを破滅させなければならなかった問題に、説明がつくはずはなく、私は言葉について考えるとばぐちをようやく探りあてたのかもしれない。 説明は簡単につく。 しかし、説明がそのものを伝えるという確証は、誰一人出来ない。 それどころか、説明すればするほど、そのものから遠ざかるということは、ごく日常の伝達においてですら、言語を発する者が感じていることなのである。 言葉はそれを発する者の全てに基づく、というようなメンタリズム、あるいはオカルティズムは、まだ私のとる立場ではないと自制している。 いまのところは、言葉とは楽器演奏や料理と同じく、物理的要素は同じでも、心の込め方で全く違うものになるのだと、薄く認識するところでとどめようとしている。 まだもう少し、言葉について考えなければいけないと、考えている。 その会の後、重松氏と「フライング・キッズ」に行って、それぞれジンを飲み、翌朝は頭痛だった。 【追記】 君がそんなに考えているとは思わなかったという沖田先生の言葉に、少しへこんだ。 無言の時間を少なからず供に過ごしたときは、互いに理解していたと思ったのに。ぃ・・・ |
||||||
| 05/02/17 | 腰ぬけの妻うつくしき巨燵かな 蕪村(「蕪村句集」冬の部) 腰抜け (1)腰に力がはいらず、立てないこと。また、その人。 (2)臆病(おくびよう)者。いくじなし。弱虫。 「―侍」 うつくし (1)(肉親に対して)しみじみとした深い愛情を感ずるありさま。いとしい。 「妻子(めこ)見ればめぐし―・し/万葉 800」 (2)(特に小さなもの・幼いものなどについて)小さくて愛らしい。かわいらしい。 「―・しきもの、瓜にかきたるちごの顔/枕草子 151」 (3)細部まできれいに整っている。申し分がない。 「大学の君その日の文―・しう作り給ひて進士になり給ひぬ/源氏(乙女)」 「炬燵で温まった細君が腰抜けのようなしどけない状態になってしまった、という光景であろうか」という解釈もあり、妥当な解釈であろう。 ほんとうに病気の妻であるとしたらどうだろうか。 立ち上がれぬ病になり、コタツに座っていることしかできない。そのような妻を、愛しいと言うのである。 しっとりとした愛情があると同時に、冷徹な美意識が感じられる。 腰が抜けて初めて見いだした美が、病になってみつけた愛しさが、あるというのである。 水仙や美人かうべをいたむらし 蕪村には病む女性の美を描く発句があるが、「腰ぬけの」句には冷酷とも感じられる目がある。 頭痛持ちの女性には水仙を取り合わせるだけなのだが、 腰ぬけの妻には「うつくし」という賛辞を与える。 相手が病んで初めて気づく、美しさ。 病むことなしには、発現しない美しさ。 |
||||||
| 05/02/14 | 高校生の小論文の選考をした。 課題文は十数年前に山田太一が書いたエッセイともつかない小文で、 若い学生の前で悩みや挫折が人間を育てると講演した後学生たちに尋ねたところ、彼らは自分たちの悩みはそれほどではないと答え、それに対して、彼らが感じている「浅薄感」こそが自分たちの出発点になるのではないか、 というものであった。 生徒たちの小論文は、どれも、いや例外なく全て、浅薄感=悩みがないこと、としていた。 それは愕然とするほどの、肩すかしだった。 選考にあたった者たちは皆愕然としていたのだが、それは、自分たちの学生時代と比較してのことで、自分たちが学生であった頃は、山田太一が問いかけたことにまだ納得のいく時代であったのだが、では、今の私たちがどうなのか。 自分の悩みが浅薄であることに退け目を感じているのか。 いや、悩みを悩みと言うことに躊躇いを感じているのではないか。 私は世代間の差違というものはないと思っている。 私たちが差違と思っているものは、何年か前の自分たちと、今、何年か前の自分と同じ年齢である者たちとの差違であって、今の自分たちとの差違ではない。 私が高校生の時はそんなことは考えなかったとか、そういう差違である。 では、今の自分と、今の若い人たちと、差違はどうあるのか。 私は、今生きているということにおいて、同世代人だと考えている。 今の高校生が、浅薄感=悩みがないことと感じているのは、じつは大人である私たちも同様なのだという気がする。 私たちが「仕事」を中心に感じている日々の葛藤は、果たして「悩み」と呼ぶに値するものか、という問いすらも素通りして、悩みではないと思っているのではないか。 意識しなくとも呼吸しているように、意識することなく生きているような、日本の社会・経済状況である。 であるとひとくくりにしてはいけないのではあるが、しょうがない、私はそうなのだ。 呼吸しようと思わずとも自然に酸素は体内に吸収され、必要な栄養分はいつの間にか摂取されている。 今日私たちが感じた落胆は、ほんとうは、自分たちの悩みが浅薄であることに悩みの原点を見いだすことより、もっと深刻な事態に立ちいたっていることを、高校生たちが無意識にでも気づいているという現状に対するものだったのかもしれない。 自分とは何かを考えなくても生涯を送っていける人生とは何か。 自分の生命が薄皮いちまいで保っているという感覚を持てずに生きている現在が、私に何を与えてくれるのか。 絶望は、より深くなっているに違いなく、高校生たちはそのことを、何十年か前に高校生であった私たちより、より深く直感しているのだろう。 その直感を言葉にするときのとまどいが、彼らに今回のような文章を書かせたのだ。 そして私たち「大人」は、過去の自分に照らし合わせて今を嘆いているだけで、ほんとうに嘆かねばならないのは、今の自分たちのはずだ。 先月、山田太一の『彌太郎さんの話』を読んだ。 人物像がうまく描けない小説だと、批判を書こうと思ったがそのままになっていた。 しかし、山田太一は十数年前の自分の考え・言葉を真摯に実行していたのだと、思う。 浅く薄っぺらな自分が、とうていとらえることのできない厚く深い、それは不可解としかいいようのないことがらに、誠心誠意真っ直ぐに対峙しようとする文章なのだと思う。 そして、私の『私たちは生きているか』は、今の高校生たちと同じ自分をなんとか位置づけようとする作業であるように思える。 よく言えば、意識しているかいないかの違いであるが、それがさほど大きなことなのかどうか、私には自信がない。 ただ、そうした「悩みがない」ことのもどかしさが、私の詩集の根底にあるはずだという自負があり、それがうまく伝わりそうもないという挫折感がある。 なんだこの詩は!? つまらん!! と言われれば、ある程度の成功なのだろう。 |
||||||
| 05/02/08 | 誰もいない薄暗く冷たい職場のトイレの中で独り言をつぶやいて、ふと気づいた。 つぶやいたのは「なにもわからぬ」という、確か『山月記』の李徴のセリフだと思うのだが、 気づいたのは、 私たち人間は、自分が何であるか知りたがる生き物ではないかということ。 人間は、(進化学的にも)人間となったときから、その問いを続けているのではないか。 哲学的に言えば、その疑問が私たちを人間たらしめているのではないか。とも言える。 ひょっとしたら、カントがすでに言っていることがこれかもしれない。 言葉は私の外側にあるという、私の感覚。 言葉は、発すると同時に発した自分自身を照らし出す。 そのように感じるのは、唯一言葉を持つ生き物である人間の特性なのではないか。 言葉は自分の外を対象化すると同時に、その対象化が自分自身に及ぶものである。 人間が魂と肉体の二元論をいまだ超克できず、あるいは聖書が始めに言葉があったと言うのは、自分が何であるか知りたがる生き物である人間の特性が、言葉という機能にあるからではないか。 養老猛司ふうに言えば、そうなるのは人間の脳のせいなのだろう。 人間の生理機能が、私たちをそうさせているのだが、それがどういう構造をしているのか、その構造が私たちをどう作り上げているのか、 言葉を探ることからもわかるのではないか。 言語学的な言葉の機能・構造を探ることではなく、言語の本質を見ることから人間の何であるかがわかるのではないか。 |
||||||
| 05/02/01 | なんだか落ち込んだ気分のままでいる。 先週の金曜日、横川でケンカした。 兄弟ゲンカはともかく、ケンカしたのは初体験かもしれない。 いや、それはケンカともいえないのだろうけれど。 きっかけはこっちだった。売ったのは向こう。 相手の手首を握りしめた腕の筋肉が、昨日まで痛んでいた。 結局午前3時半まで一緒に飲んで、携帯番号を交わして帰ったのだが、 翌日は散々で、夕方から翌日曜の午(ひる)前まで、15時間以上寝ていたのだが。 ---もっともそれは、1月に一人飲み会の1回を含めて9回も飲んでいたせいでもあるが。 人間は、正義では動かないと思っている。 正邪より、損得で動くと思っていた。 しかし、本当のところは、気が済む済まないで動いているのではないかと思い始めている。 先週の金曜日にケンカした相手のミキさんは、理屈は(正直言って)へちゃめちゃだった(と思う)。 しかし、彼の思い・気持ちはその時ビンビンに伝わってきていた。 だから私は、これまですることのなかった肉体的手段に出たし、彼を責めずに一緒に飲んでいた同僚を怒鳴ったし、本気で涙を流した。 気が済む/済まないということは、「情動/パトス」と言われるのだろう。 正義とか、理屈というのは「ロゴス」であろう。 パトスでケンカを売っている相手に対してロゴスはいかようにも通用しない。 それより私は彼を抱きしめたかった。 しかし、それより、我が腕が痛むのが切ない。 自分の腕の筋肉が痛むほどに彼の手首を握っていたのかと思うと、彼もまた痛くてしようがないのではないか。 イエスをはじめ、仏陀や孔子が、あれほどムキになって教えを説いたのも、「気が済む/済まない」で私たちが動いているからなのかもしれない。 そして彼らは、それに対してあきらめの表情をうかべながら、許したのだろう。 自分は道を示せばそれでよい。いや、それ以上のことはできない、と。 あの時のミキさんの思いを言葉にしようとすれば、できなくはない。 しかしそれは、それ以上のことではない。 ミキさんと今後つきあっていけるのかどうか、そんなことはわからない。 ただ、出会いがあったことだけが確かだ。 そういえば、彼は因島の出だという。 因島といえば村上水軍で、小学校の時のユースケ君は村上姓だった。 何となく顔立ちが似ている気がする。 新たな再会、なのかもしれない。 ケンカしたスタンドのマスターは同郷の草津の出身だと言うし、何週間後にはまた行くことになるだろうな。 |
||||||
| 05/01/19 | 昨日の続きはまだなのだが。 そんなことを書く気持ちがなえている。 なんだか、小さい世界で小さいことを言っている気分、と言おうか。 抗生物質で風邪が気管支炎になるのを抑えている。 昨年の11月の時は、本当に苦しかった。 息を吸うことはおろか、吐くこともできなかった。あの苦しさが、恐ろしい。 で、医者から抗生物質をもらって飲んでいる。 それもどうでもいいことかもしれない。 そんな、新年早々に消耗した体で、仕事から帰りに駐車場に向かうときに見上げた夜の雲に、こんな風景と同化した日々があったことを、思い出した。 私は今、『私たちは生きているか』という詩集をなんとか仕上げようと、一昨年の暮れから苦闘している。 しかし、そのタイトルの意味するところは、じつは、私が、生きていることを見失っているからなのだ。 夜の雲と同化したあの頃から、遠く離れたのかもしれない。 私のまわりにあるさまざまなものや現象から自分が触発されることは、それこそ、自分が生きていること、だったのかもしれない。 一昨年の暮れに『私たちは生きているか』というタイトル(コンセプト)を発見したことは、 逆に私が生きていることから遠ざかっていることだったのかもしれない。 そして私は、急性虫垂炎で腹膜炎寸前のところで手術入院した。 そして、私は、反射で日々に対処していることに気づき、違和感を感じている。 これはどうすればいいのかと、まわりを見回し、しどろもどろに対処していた頃とは大違いだ。 それがもどかしい。 どんな音楽を聴いても、しっくりこない。 ボゥイも、ブラッフォードも。マイルスはなんだか怖い気がして聞いていない。 ジェーン・バーキンを聞いている。 彼女は六十を過ぎたのだろうか。 ゲーンズブールは亡くなり、シャルロットは三十になったのだろうか。 バーキンを聞くと、少しだけ落ち着く気がする。 『私たちは生きているか』は、こんなふうに追いつめられた私が、追いつめられたところから、夜の雲に同化する存在を見つめる詩集になるのだろうか。 昨年の正月から、言葉はひとつも進んではいない。 詩集が完成する気配は何もない。 話は飛ぶ。 今「何もない」と書いたとき、「なに」を「何」と漢字に変換したとき、 『Replay』という詩を書いた高校生の時の気分がよみがえった気がした。 もはやその原稿も失い、「インクスポット、藤の花」とか「リ・プレイ、リ・プレイ」といったフレーズしか思い出せないのだが、 「なに」を「何」と漢字書きした気分が、バーキンの歌声の薄皮の上や下に、実在として存在する。 こうして文章を書いても、もどかしい。 詩は視線である、というのは、詩には「今」しかないということであろう。 時が一瞬でも過ぎれば、視線を見ている視線しか残らない。 詩は、永遠に「今」であり続ける。 私は「今」を過去や、未来という幻想の中に見つけ、言葉として定着するのだろう。 そして言葉は、過去や未来を表そうとしているがゆえに、幻想のように時間や空間を漂い続けるのだろう。 それは、私が理想とする詩なのかもしれない。 |
||||||
| 05/01/18 | たばこ多いほど自殺の危険(共同通信)
日本人の中年男性では、1日に吸うたばこの本数が多いほど自殺する危険性が高まるとする大規模疫学調査の結果を、厚生労働省研究班がまとめた。21日から大津市で開かれる日本疫学会で発表する�。研究班は「たばこと自殺の関係は未解明の点が多い。禁煙で自殺が減るかどうかも研究課題だが、喫煙本数の多い人の心の健康に注意することは、自殺予防対策に有効だろう」としている。
[共同通信社:2005年01月17日 16時25分]->リンクはここ 「煙草吸い」(常習的喫煙者)は、こんなことは気にしていない。 |
||||||
| 05/01/11 | とりあえずこれから書きたいことを列挙しておく。 ・昨日の記事の続き。一昨年から書き始めた『私たちは生きているか』は、この認識の上に成り立つ。 ・マーラーよりベートーベンの方が、どう聞いても「へん」だ。すれすれのぎりぎりだ。それは、小林秀雄が「モオツァルト」で書いていたことのとおりだ。 ・映画『マトリックス』で主要登場人物がサングラスを掛けているのは、『サル学で見る人の未来−人間性の進化史;正高信男』で合点がいった。「マトリックス」の世界は、記号の世界であり、記号であるかぎりそれは言語の世界であり、言語の世界ということは視覚を制限するということ。 ・ネットワーク接続を切断しよう。窓の中も理解不能でいっぱいだけど、窓の外は、理解不能がいっぱいで楽しいぞ。わかる理解不能だけ見ているつもりかい? あと、今思いついたが、日本はまだ江戸時代か?・・・・これは、結論は見えてるか・・・ |
||||||
| 05/01/10 | NHK7時のニュースを見ても、「女子アナNG大放出」を見ても、どれも同じに見える。 今年は終戦60周年だそうな。 「終戦」と言うか「敗戦」と言うか議論があるのは承知だが、8月15日を「記念日」として、天皇臨席の記念祭をしているかぎり、「終戦」という言い方は残り続ける。 昨年に引き続き、広島大学ロック同好会OB新年会「リセット」に参加した。 江藤淳「閉ざされた言語空間」、吉本隆明「『ならず者国家』試論」、テレビ「戦後60年新春特別企画ビートたけしの陰謀のシナリオ!!日本を震撼させた戦後7大事件はアメリカの陰謀!?SP」の影響でもあるのだが、 終戦だろうが敗戦だろうが、アメリカ傀儡政権60周年であることにちがいはない。 私は、だからどうだと言うのではない。 第2次大戦後のイギリスは、戦勝国とはいえ、アメリカ文明の怒濤のごとき流入にさらされざるをえなかった。 |
||||||
| 04/12/13 | 昨日の続きでカーナビにダウンロードした山下達郎を聞いていた。 「さよなら夏の日-カラオケバージョン」(Rarities)を口ずさみながら聞いていると、信号が赤になった。 哀れに思ったのではない。「さよなら夏の日」があまりに合っていたのだ。 それはどういうことなのだろう。しばらく考えた。 人間は、「大人」になるのではない。「中年」になり、「老人」になるのではない。 「さよなら夏の日」が歌っているのは、「夕立のプール」とか少年の夏の日の恋ではなく、誰もが通る「あの時」なのであって、「あの時」は私の前をたどたどしくゆっくり横切った老婦人にもあるわけで、 たぶんそんなわけで涙がにじんだのだろうと思った。 解説や理屈はどうでもよい。そういう人と出会ったのだ。 いろいろと思いをめぐらしたあと、ゆっくりと横断歩道を渡り終えた婦人にもう一度目を向けると、また涙がにじんできた。 信号が青に変わっていた。アクセルを踏んだ。 |
||||||
| 04/11/25 | 自分の音楽の守備範囲は、広いのか狭いのかよく分からない。 広いといえば広い。 現代音楽から、アイドルポップスまで。 でも、こまかいところはよく知らない・・・・・・・あ、広く浅く、か。 きょう夕方、アバンセ古江店で寿司とトンカツと豆乳コーヒー味とネギエピを買い、その向かいの酒屋で、八幡川「吟醸 四季暦」とジョニ黒を五千円札を出して買っているときに思ったこと。 アバンセ古江店では思わなかったのだが、向かいの酒屋では思ったのだ。 日本銀行券という印刷された紙を出して、物をもらう。 なんだかごっこ遊びみたいだ、と。 アバンセ古江店では思わなかったのに、その酒屋で思ったのは、酒屋の若主人のだるそうな雰囲気のせいだったのだろう。 アバンセ古江店のレジの女性たちは、懸命にその「役割」を果たそうとしていたが、 酒屋のだるそうな主人は物と銀行券を交換していた。 物を右から左に動かせば、お金が左から右へ動く。 ただそれだけで、私たちの生が保たれている。 これは正常なことだろうか。 アバンセ古江店の向かいの酒屋の若主人のだるそうな雰囲気は、私の奥底にある疑問とシンクロしていた。 「冬のソナタ」の挿入曲2曲の指揮を五日前に終えて、なんだか現代音楽ばかり聴いている。 今日の行き帰りの車のBGMは、坂本龍一の「Chasm」。ポップスであると同時に現代音楽。 昨日はオリビエ・メシアンの「遠い閃光」・・・・・・・第1楽章はグレゴリオ聖歌だよな、鳥の声だけの楽章もあるし、とても絵画的、音楽を聴いて鮮やかな色彩を感じたのは、たぶんはじめての経験のように思う。 たとえば、物と日本銀行券を交換して成り立つような生に対して、何らかの疑問をもつような人間にとって、いわゆる「現代音楽」はBGMとして成立するのではないか。 逆に言えば、そういう人間にとってBGMとして聴かれる音楽が「現代音楽」なのかもしれない。 「現代音楽」の一見難解な音響は、「そこにある音」として聴いてしまえば何のことはない。 意味を求めることから始めて音楽を聴こうとすると、理解がこんがらがる。 音は厳然としてそこにある。それは、山や川や海と同じように。 私たちは意味を求めて山や川や海を見るのではない。見るところから意味の解析が始まる。 意味を解析するところに、私たちの存在がある。 買うという行為は、物と銀行券を交換する行為である。 と認識することは、現代音楽を聴く行為と、それほど遠いことではないと思う。 |
||||||
| 04/10/28 | NHK教育2004年10月28日19時55分から放送された「まいにちスクスク」にオブジェクション。 乳児のためのキッチン鋏の活用法を紹介していたのだが、食べさせようとしていたのが、 うどん スパゲティ のりまき サンドウィッチ ・・・・・・・・・・・・ ちょっと待て! 離乳食ちょっと過ぎの子に、何を食わせようってんだ。 大人の食べ物と子どもの食べ物はちがって当たり前じゃないか。 そのうえ、持ち運びできて、分解できれば、洗って衛生的、ときた。 ちょっと途中から見たので、子どものためにそんなものを食べさせようという主張かと思ったが、 結局ファミレスやなんかで、自分たちの食べているものをそのまま食べさせると、楽だというだけじゃないか。 離乳食ちょっと過ぎの子に、大人と同じものを食べさせるという発想自体が、間違っている。 「奥薗式!ズボラ離乳食」だと! 子どものことを考えないことが、ズボラの正体だとしたら、これは犯罪だ。 言わずもがなのことだが、 子どもには子ども向けの味付けをするべきだ。 それは、子どもの栄養摂取や味覚の発達を考慮してのこと。 そして、大人の食べるものは難しいという感覚を与えること。 それらを食べることができときに、成長したという感激を味わえるのではないか。 「奥薗」はそうした感動を味わったことはないのか!? NHKはこうした犯罪を、平気で犯している。 |
||||||
| 04/10/25 | ・目に見える大事なもの ・目に見えない大事なもの という命題を目にした。 目に見える、とはどういうことだろう。 私は、じつはビート、あるいはテンポが、視覚として感じられる。 また、目の前にあっても、それと認識できないことがあることを、私たちはよく知っている。 目に見えないものを認識するということは、目に見えるものを充分に認識することであり、 目に見えるものをそれと認識するということは、目に見えない部分を認識しようと努力することではないか。 私たちは、目だけで見ているのではないのである。 |
||||||
| 04/10/25 | 新潟中越地震の被害の甚大さは、人が散在している山間部を襲ったところにあるのだが、阪神淡路大震災のときにも思ったことを、書いてみる。 マスコミが報道することは、被害の様相であり、死者の数である。 今回、NHKが教育放送やFMで個人連絡を受け付け流しているが、ほとんどが被害地域外からのメッセージで、それは受け付けが受け身型だからだ。 これだけ災害現場に入りこみ取材するのなら、生きている人のナマのメッセージを流せないだろうか。 システム上困難な点もあるのは分かるが、一番の困難なのは、「マスコミ」自体が抱えている「システム」であるのは明白である。 売れるものを送る、それしか、この「システム」にはない。 私がアナウンサーとして現場にでかけているなら、その場にいる人たちに名前を聞き、その人たちのメッセージを直接に流したい。 一人10〜15秒でもいい、それを24時間流し続けたい。 報道というのは、いったい何なのだ? メディアというのは、実態は「管」ではないのか? 管を管として有効に使うことが、メディア従事者の使命ではないのか? 多くの人が不安な時を過ごしているときに、被害の実態を伝えることも否定しないが、それを見ている私たちは、安全な場所にいて、同情という名の安心感を感じているだけなのではないか。 そういう私たち被害地域外にいる大多数を無視してでも、いま困難に直面している人たちのために、少なくともその人たちの安心感のために、この極めて有効であると思われている「管」=メディアを使うべきではないか。 |
||||||
| 04/10/18 | 「消費者」とは、差別のない世界である。 消費する者の何にも拠ることなく、「消費者」と呼ばれる。 性別、年齢、学歴、私たち日本社会の中にいる者が今直面している、よりどころのなさ、とりとめのない崩壊感は、ここに由来しているのではないか。 フェミニズムの主張があたりまえになされ、消費の動向の一端を「子ども」たちがにぎり、TV-CMからかつてのような父親像が消え去っていったのは、70年代から始まり、80年代にミキサーにかけられて混沌とし眩惑し、90年代に再編成し始めた現在だからなのである。 すべて平等である。 法の下の平等と言ったが、今は消費に基づいた平等である。 では、消費の多寡による差別はあるのか。 いま私は、それはないのではないかという思いと、あるような気がするという予感のあいだにいる。 「バブル経済」が終息して、不景気、あるいはデフレスパイラルと呼ばれる状態を、いまだに脱しきっていないが、それは、ゴム紐に目盛りを刻んでいただけで、伸びたゴム紐が縮んだだけである。 1メートルを10に刻んでいたのを、10センチメートルを10に刻んでいるのが、「バブル」後の今なのである。 実測値でいえば、「バブル」期に10センチメートル消費していた者が、今は1センチメートル消費しているのであるが、モノサシの上では、何らの変わりもない。 交換されうるものを阻害しないことというモノサシの上では、なおさら、1センチメートルと10センチメートルの差は、ない。 「生産」は、具体的な体力や技量というものの上に成り立つものである。 より短時間に、より多量に、より高品質なものを作ることが、よりよい「生産」である。 そこでは、生産する者の差が拡大される。 では、より多量に消費する者が、よりよい「消費者」なのであろうか。 ゴム紐のモノサシが縮んだ今、「消費すること」を実行することが「消費者」の資格であり、それが1円であろうが、1000万円であろうが、本質的には変わらない状況にあるのではないか。 もちろん、全地球的に見たときに、このことの矛盾は露呈してくるのだが、21世紀初頭の日本の状況は、だいたい、こういうところではないのだろうか。 |
||||||
| 04/10/17 | 前項の補足。 「消費者」という位置づけは不思議だ。 すべての人間が生産者ではないが、すべての人間が消費者なのだ。 人口の過半数が第3次産業従事者になったということは、「生産<=>消費」という流れを消費者が握ったということであり、生産より消費の方が重要、という価値観が、自然に作られることになったと言えると思う。 |
||||||
| 04/10/15 | 第3次産業の定義は、 『大辞林』では、「C =クラークによる産業分類の一。商業・運輸・通信・金融・公務・サービス業などをいう。日本の統計では電気・ガス・水道業を含める。三次産業。」 簡便な理解として、物を作らない産業、としてもいいと思う。 物を作らない産業とは、物を右から左へ動かすことで利益を得る産業ということだ。 それは、古典的な理解で言えば、生産者と消費者の距離を埋める産業ということになるだろう。 しかし、第1次・第2次産業従事者が人口の半数を割ったとき、それらの生産の場が、半数以上の人々の視野から霞んでいったのではないか。 かまぼこは板に乗って海で泳いでいるとか、ハムは木になっているとか、冗談半分で言われていた嘆きが、じつは大きな意味を持っていたのかもしれない。 生産の場が視野から外れていったとき、日本におとずれたのが「バブル経済」であり、 「バブル経済」で経験したことは、物が動くことが経済だという理解である。 生産は、国民の半数以下を占めるだれかにやらせておけばいい、東南アジアの低賃金で働くだれかにやらせておけばいい、物を動かせば、物と反対方向にお金が動き、右へ動かしたお金以上のお金が左から入ってくる。 こうした理解が、「バブル経済」によって作られた。 それは、けっして誤った理解ではなかった。経済というものの抽象化された理解として、そしてそれが国民規模でなされたという点で、正当性を保持していると思う。 私は、バブル以前の産業観へ戻れと言う気はない。言ったとして、戻れないだろう。 米の自由化から始まった経済構造の中における農業あるいは農業観の変貌が、それを示している。 物を作ることが、経済ではない。 生産と消費が結びついて経済が成立するという、ごく単純な理論に、日本人が、自覚的にせよ無自覚的にせよ、気づいたのだ。 戦前は1割程度であった大学卒が、8割近くを占めるということは、物を動かすことが経済の本質であり、日本が経済主義国家である以上、物を動かす職に就くことが主流であり、そのためには大学卒でなければならない(あるいはそれが楽だ)と、直感したからだ。 生産の場から離れ、あるいは生産自体が物が動くという現象に限りなく近寄った現在、 その動きを阻害しないことが、第一義的モラルとして成立しているのは当然のことなのである。 |
||||||
| 04/10/14 | 昨日の発想を、少しずつ進めてみたい。 ・ 「全て交換されうるものを阻害しないこと」というモラル。 ・交換されることだけが、唯一の問題である。 ・等価であるかどうかすら問題ではない。 これらが私の発想の根幹である。 交換とは、価値が考えられていなければ成立しにくい問題であるが、その価値すらが、交換されるということにおいて成り立っているのである。 さらに言えば、交換の可能性を持つことで、すでに価値を持っているのである。 これまでの考えであれば、価値は、労働力・時間とそのものの多寡によって決定されていた。 しかしそういった発想によって裏付けられた価値というものは、たんなる約束事であり、真の価値とはなり得ない。 そして、そうした価値でさえ、交換され得るという可能性がなければ、価値があるとは言えない。 その意味で、等価であるかどうかすら問題ではないのである。 有り体に言えば、生産<->消費という体系の中に求められる価値ではないのである。 ネット上で交換される情報が、どのような形を取っているかを考えれば、それはあきらかである。 どのような思想も、感情も、知識、情報も、受け手側のPCによって決定づけられたフォントによってしか目の前に表れない。 さらに言えば、どのようなそれらも(文字であれ、画像であれ、音であれ)、2進法による記号にすぎない。 現実的な話をすれば、文字であれ、画像であれ、音であれ、その内容の如何を問わず、通信料に帰結する。 さらに、月額定額料金であれば、どの情報も、等価なのである。 かつては、私たちが今目の前にしているホームページや、掲示板や、チャットがとっている、フォントによる表示というのは、フォント(活字)にするだけの価値ある内容であるか、内容がなければそれだけの代価を払わなければ、そうはならなかったものなのである。 それが、1台十数万円(・・・かつては数十万円、だった・・・)のPCと、月々2、3千円の代価で、なされているのである。 たしかに、凸版印刷による豪華本という可能性もあるが、それも、1台十数万円と月々2、3千円の延長線上にあるのである。 私が言う「等価」とはそういう意味であり、すべてが等価であれば、等価であるかどうかということは、問題にすらなりはしない。 |
||||||
| 04/10/13 | 『現代詩手帖』を求めて、久しぶりに本通りにでかけた。 福屋脇の金座街を歩いていて、微かなときめきを感じて、 私(たち)は、お金と物を交換することが好きなのではないか、と思った。 私たちの社会は、必要に迫られてこうなったのではなく、私たちがそうしたいことが作り上げたのではないだろうか。 お金と物を交換することが好きな私たちの作り上げている社会のモラルとは、 お金と物の交換を阻害しないこと につきるのではないか。 第3次産業従事者が就労人口の半数を超えた時期に思春期をむかえた私と同世代が親となった現在、そのモラルが、原点となっているのは間違いないような気がする。 「お金と物との交換を阻害しないこと」をモラルの原点に据えれば、年齢による差異も、性別による差異も、そしてじつは貧富の差異(「貧富の差」ではない)も、なくなる。 さらにその先に、情報化社会があり、 情報化社会とは、情報がお金や物と同じあつかわれ方をする社会のことではないか。 「全て交換されうるものを阻害しないこと」と、今や言い換えられているのではないか。 交換とは、けっして等価交換のみを意味するのではなく、例えば「お裾分け」や「ポトラッチ」も交換であると考えれば、 現在ネット上でなされている情報の氾濫は、まさに「お裾分け」や「ポトラッチ」の交換である。 しかもその交換が、「全て交換されうるものを阻害しないこと」というモラルの上に成り立っているので、第1次・第2次産業を基盤としたモラル上では、ほとんど理解不能な状況になっている。 つまり、交換されるものが、生産上・消費上(=生命維持上)価値のあるものであるかどうかは、問題とされない。 価値の有無を問わず、交換されることだけが、唯一の問題なのである。 そして、逆にそのことに価値が生じている。 等価であるかどうかすら問題ではない。 そう考えていくと、昨今の親子の癒着ぶりも理解できるのではないか。 子どもたちを含めた私たちの言動も、理解できるのではないか。 『現代詩手帖』は手に入らなかったが、さがしていた文春文庫版『考えるヒント(4)』が手に入った。 『現代詩手帖』を読んで考えたいことは、また次の機会にゆずることになった。 |
||||||
| 04/10/11 | ほとんどたんなる、いちゃもんである。 一方、かつてミリバールで表していた気圧の単位は国際単位のヘクトパスカルに変わった。もう十年以上も前のことで、すっかり耳慣れた。時代とともに変わるモノサシもある。 (2004年10月6日付け中国新聞「天風録」) ヘクトパスカル[hectopascal] 圧力の SI 単位パスカルの一〇〇倍に相当する呼称。一ヘクトパスカルは一ミリバールに等しい。記号 hPa (「大辞林」) モノサシは変わってはいない。 単位の呼称が変わっただけである。 たとえば、もし、デノミネーションが実施されたとする。 (これまでの)100円=(これからの)1円 これは、モノサシが変わったと言える。 しかし、 (これまでの)1円=(これからは)1J$(Japanese Dollar) では、モノサシは変わってはいないのではないか? だからどうのこうのとは、言う気すらないが。 変わるモノサシがあるとして、だからどうだというのだ? 論になっていない。 |
||||||
| 04/10/04 | Windows XP Sevice Pack2をアンインストールした。 Giga Pocket録再時や、DVD再生時の、外付けHDへのアクセス不良がおさまった。 これが建物なら、継ぎ足しに継ぎ足しで、とんでもない格好になっているにちがいない。 2階から1階のトイレへ行くのに、非常階段を下りて近くのバス停でバスに乗り、みたいになっているイメージ。 News23で、坂本龍一の「War And Peace」の日本語版を初演した。 戦争を求める言葉は切実なのに、平和を求める言葉・戦争を批難する言葉は、なぜ空疎に響くのだろう。 戦争は現実であり、平和は観念でしかないからなのだろうか。 戦争も平和も、じつは、自分は生きたい、せめて自分だけは生きたい、という欲求の現実的現象なのではないか。 であれば、切実さの問題になる。 戦争は人を殺しても自分は生きることであり、平和は自分が殺されないことであるなら、戦争の方が切実さが勝っているのは明らかではないか。 もうやめようよと言っても、誰が自分の生命をほんとうの意味で保障してくれるのか。 平和とは、自分は誰も殺さないという意思表示でしかないのではないだろうか。 聖フランチェスコの「平和を求める祈り」が胸を打つのは、あくまでも自分の意思の表明に徹しているからだ。 戦争を生きのびた人たちの反戦・非戦の言葉が重みを持つのも、それと同じところにあるのではないか。 戦争を批難しても、平和は訪れない。 |
||||||
| 04/09/29 | 昔のことを思い出して、胸苦しくなることがある。 なにか大事なこと、楽しかったことがあったはずなのに、思い出せない。 情景や、そのときの感情は強くよみがえり、その詳細は思い出したつもりになるのだが、それがいつのことなのか、どこでのことなのか、「記録的」には思い出せない。 冷静に考えれば、23年前も今も、同じことをくり返しているにすぎない。 何も変わってはいない。 今も昔も、「クライアント」との葛藤の毎日であり、社内の人的摩擦がくり返されているだけだ。 それでも、先月末に20年ぶりに会った「おにいちゃん」から、その当時の話を聞いて、そのことをすっかり忘れていたりしていると、不安になる。 不安になるのは、忘れていることがあるという事実ではなく、あったことが思い出せないということ。 あったことは覚えているのに、その詳細が思い出せないこと。 そして、その覚えていること自体が、つくりごとであることが、そして、つくりごとにむなさわぎを覚え苦しくなることが、私の何であるかを指し示すような気がする。 私は何をしてきたのか、と中也のような問を思うが、 |
||||||
| 04/09/21 |
|
||||||
| 04/09/20 |
|
||||||
| 04/09/16 | 三日続けて同じ話題。 長崎の事件の加害者の処分が決まった。 中国新聞の一面記事に解説の見出しは「『資質』を強調/心の闇迫れず」とある。 同紙33面に江川紹子氏のコメントとして、 決定内容を見てもなぜこの事件が起きてしまったのかよく分からず、歯がゆい。・・・(中略)・・・などのコミュニケーション能力を育てる機会が、携帯電話の普及やインターネットの発達により失われている。大人社会が子どもの世界を浸食している。・・・(後略) とある。 言っていることは、私の論と変わるところはない。 また、長崎家庭裁判所佐世保支部の決定要旨でも、インターネットや、コミュニケーション能力に関してこの件を理解しようとしている。 長崎県佐世保市の小6女児事件で、長崎家裁佐世保支部が15日出した決定要旨は次の通り。 【主文】 女児を児童自立支援施設に送致する。2004年9月15日から2年間、強制的措置をとることができる。 【非行事実】 女児は長崎県佐世保市の小学校6年に在籍、同級生の被害者=当時(12)=とは交換ノートやインターネット上でメールをやりとりするなどの交流をもっていたが、被害者が交換ノートやホームページに記した内容を見ているうちに、自分をばかにし批判しているように感じて立腹し、怒りを募らせた揚げ句、殺害しようと決意し、04年6月1日午後零時20分ごろ、小学校3階学習ルームで、右手に持ったカッターナイフで被害者の頚部(けいぶ)などを切りつけ、間もなくその場で失血死させ殺害した。 【人格特性】 ▽認知・情報処理特性 女児は生来的に(1)対人的なことに注意が向きづらい特性(2)物事を断片的にとらえる傾向(3)抽象的なものを言語化することの不器用さ(4)聴覚的な情報よりも視覚的な情報のほうが処理しやすい−−といった特性がある。そのため自分の中にあるあいまいなものを分析し、統合して言語化するという一連の作業(例えば感情の認知とその言語化)が苦手である。 なお(1)ないし(4)の特性は、広汎性発達障害や受容性表出性言語障害などに多く見られるものである。しかし女児の特性は軽度で、上記各障害やその他の障害を診断される程度には至らない。 ▽情緒的特性 女児は上記各特性の中でも(1)の対人的なことに注意が向きづらい特性のため、幼少期より泣くことが少なく、おんぶや抱っこをせがんで甘えることもなく、1人でおもちゃで遊んだり、テレビを見たりして過ごすことが多いなど、自発的な欲求の表現に乏しく、対人行動は受動的だった。 家族はこのような女児の行動を「育てやすさ」「1人で過ごすことを好む」ととらえ、ささいな表情の変化や行動に表れる欲求を受け止め、積極にかかわることをしてこなかった。 その結果、女児は、自分の欲求や感情を受け止めてくれる他者がいるという基本的な安心感が希薄で、他者に対する愛着を形成しにくかった。そのため基本的な安心感や愛着を基盤とする対人関係や社会性、共感性の発達も未熟である。 また情緒的な分化が進んでおらず、情動に乏しい。愉快な感情は認知し表現できるものの、その他の感情の認知・表現は困難で、とくに後記の通り怒り、寂しさ、悲しさといった不快感情は未分化で、適切に処理されないまま抑圧されていた。 ▽対人関係の特性 女児は上記の特性から、主観的・情緒的なことを具体的に表現することが苦手である。また言葉や文章の一部にとらわれやすく、文章の文脈やある作品がもつメッセージ性などを読み取ることができない。その上、例えば、相手の個々の言動から相手の人物像を把握するなど、断片的な出来事から統合されたイメージを形成することが困難なため、他者の視点に立ってその感情や考えを想像し共感する力や、他者との間に親密な関係を作る力が育っていない。 また女児は、聴覚的な情報よりも視覚的な情報の方が処理しやすい特性により、聴覚的な情報が中心となる会話によるコミュニケーションでは上記の文脈理解等の不器用さが際立ち、発話者の意図を理解して返答したり、自分の気持ちをうまく表現することができなかった。 このような女児の不器用さは周囲に気付かれておらず、家庭でも学校でも女児の表現できない思いがくみ取られることはなかった。 ▽怒りの自覚とその対処方法の二極化 上記のとおり、女児は情緒的な分化が進んでおらず、愉快な感情以外の感情表現は乏しかった。そのため周囲から、おとなしいが明るい子として評されていた。 女児は成長に伴い認知機能が発達した4年生の終わりごろから、不快感情のうち、怒りの感情を認知できるようになった。ただし複雑な対人関係に起因する怨恨(えんこん)のような発展的な怒りを認知できるほど、情緒や認知機能は発達していない。 女児は怒りを認知しても、感情認知自体が未熟であることや社会的スキルの低さのために怒りを適切に処理することができず、怒りを抑圧・回避するか、相手を攻撃して怒りを発散するかという両極端な対処しかできなかった。そのため徐々に同級生らから「怒ると怖い子」として評されるようになった。 女児には、怒りを回避する時に空想に逃避する傾向や、強い怒りを急に感じたときの行動を問われても想起できない場合があることなどからすると、時には、短時間、自分の処理できない強い怒りの反応として生じる解離状態となって攻撃衝動の抑制も困難になると推測される。 ▽精神病性の障害等の有無 以上の特性はいずれも重篤ではなく、何らかの障害と診断される程度には至らない。 またこれらの特性は、人生のある時期から生じた何らかの狭義の精神病性の認知や情動の変化であるとは考えにくい。従って統合失調症をはじめとする精神病性の障害の存在は否定される。 【処遇の決定】 女児は、認知面・情緒面に偏りがあり、不快感情、特に怒りについては回避するか相手を攻撃するかという両極端な対処しかできないといった人格特性をもつとともに、傾倒していたホラー小説等の影響により、攻撃的な自我を肥大化させていた。上記特性により会話でのコミュニケーションが不器用な女児にとって、交換ノートやインターネットが唯一安心して自己を表現し、存在感を確認できる「居場所」になっていた。被害者は、女児がオリジナリティーやルールに対する強いこだわりから、女児の表現を無断使用するなと注意してくることに息苦しさや反発を覚え、女児に対する反論を交換ノートに記し、ホームページに名指しを避けながらも女児への否定的な感情を率直に表現したとみられる文章を掲載した。 女児はこれを「居場所」への侵入ととらえて怒りを覚え、いったん回避的に対処したものの、さらに被害者による侵入が重なったと感じて怒りを募らせて攻撃性を高め、とうとう確定的殺意を抱くに至り、計画的に本件殺害行為に及んだ。 被害者の言動は、他人をして殺意を抱かせるようなものでは決してなく、特段の落ち度は認められない。しかし女児が被害者に対する怒りを募らせた末取った行動により、かけがえのない生命が奪われてしまったのであり、その結果はまことに重大かつ悲惨である。 女児は、本件行為当日に一時保護され、その後3カ月余りにわたり、観護措置や鑑定留置による身柄拘束を受ける中で、裁判官、家庭裁判所調査官、鑑定医、鑑別技官、さらには付添人や保護者らから、本件触法行為を中心に、数え切れないほど多数回にわたり問いかけをされ、自ら行った重大行為について振り返り、内省する時間と機会を十分持った。その中で、女児なりに努力する様子を見せたものの、その人格特性ともあいまって、現在に至ってもなお、自らの手で被害者の命を奪ったことの重大性やその家族の悲しみを実感することができないでいる。 その背景には、前述の通り、女児は、愛着やこれを基盤とする共感性に乏しいことから、自己の悲しみの経験や共感性を基盤にした「死のイメージ」が希薄であるため、女児にとって人の死とは「いなくなる」という現象以上に情動を伴うものになり得ていないことが挙げられる。 また、女児が贖罪(しょくざい)の意識を持ちがたい背景には、殺害行為に着手した直後に解離状態に陥ったことで、本件触法行為に現実感がなく、また実行行為の大半の記憶が欠損していること、処理しかねる強い情動には目を向けないようにして抑圧する対処が習慣化していることなども指摘されよう。 今後、女児が、健全な人格を形成し、本件触法行為の重大性を認識し、贖罪の意識を持つためには、女児の資質上の問題点を解決するよりほかにない。そのためには、女児に、まず、情緒的な受容体験に基づく基本的信頼関係を獲得させ、その後に、感情や情動の認知とその処理方法、自己の意思を伝達する方法等の社会的スキルを習得させる必要がある。 一方、女児の両親は、女児の身の回りの世話など通常の監護養育のほかに、教育面にも関心を持って接してきたことが認められるものの、情緒的な働きかけは十分でなく、おとなしく手のかからない子であるとして女児の問題性を見過ごしてきた。 もっとも、女児が2歳の誕生日を迎える直前ごろに父親が長期間の入院生活を余儀なくされ、父親の関心は、闘病生活と就職に、母親の関心は、夫の病状のほか、生活を維持するための就労などに向かわざるを得なかったという、女児にとってもまたその両親にとっても不幸な出来事があったことは事実である。 このような事情があったとはいえ、両親の監護養育態度は女児の資質上の問題に影響を与えている。両親は今回の手続きの中で、女児の資質上の問題や自分らの養育態度に不十分な点があったことなどを知らされ、理解を深め、改めるべき点は改めようとする態度に変化しつつあるが、直ちに改善されるとは考えられない。 以上からすると、女児の家庭には、女児の資質上の問題を解消できるだけの機能が備わっておらず、事案の重大性にかんがみても、女児に対し社会内処遇をもって臨むことは不可能である。そして、女児は、14歳未満であることから、女児を児童自立支援施設に収容するほかない。 ただし、現段階では、社会的スキルの習得が不十分な女児に対して、児童自立支援施設における本来的処遇である集団内処遇を実施すれば、対人関係の行き違いから女児が他の児童に危害を加える可能性を否定できない。また、女児に、人に共感したり、親密な人間関係を築くために必要な基本的信頼感を体得させ、自己の意思を伝達する方法等の社会的スキルを習得させるためには、まず、情緒的な応答性の高い、受容的な母親的存在との2者関係から再体験させていく必要があり、個別処遇が求められるところである。 加えて、女児は、現在は本件触法行為に対して現実感を持ち合わせておらず、情緒的葛藤(かっとう)はないと思われるが、今後の処遇により、共感性などを獲得すれば、本件触法行為の意味を次第に理解するようになり、情緒的な混乱を引き起こし、自傷行為に及ぶ可能性もある。 以上のとおり、女児には個別処遇が望まれ、現段階では女児の行動変化を予測できず、女児の他害・自傷の可能性があることも考えあわせると、女児には強制的措置が必要である。 そして、女児の抱えている困難は根深く、女児の感情はまだまだ未分化で、内面的には極めて幼い状態であり、基本的信頼感を獲得するにも相当時間を要すると思われること、女児が不快と感じた状況下で逃避的な空想を展開する傾向は長い期間を経て固定されたものであり、今後の処遇における妨げになりうること等から、個別処遇期間は相当長期にわたると考えられる。一方、女児は、現在小学校6年生で、前思春期にあり、心身の変化に富む時期であるため、今後の成長により、処遇が順調に進むことも期待できる。上記諸事情を勘案すると、女児に対し、差し当たって2年間の強制的措置を許可することが相当である。 私が考えているのは、なぜ頸動脈あたりをカッターナイフで(ある程度の)力を入れてなぞったかである。 どう見ても考えても、(今の)大人はこの出来事を自分の中に位置づける方法を見失っている。 全ての人が言っていることは、どれも正しい。「正論」と言う以上に正しい。 私は、なぜ加害者がカッターナイフで(ある程度の)力を入れて被害者の頚部をなぞったか、知りたい。 加害者は、そうすれば確実に死ぬことを知っていたのか。(知り合いの消防士によれば、心臓が3回動けば致死量に至るだけの血液が頸動脈から消失されるということだ。) あるいは、それは、加害者の中では「儀式」として考えられていたのか。つまり、頸動脈を刃物でなぞれば死ぬという知識ないし認識があり、かつ実際に死ぬということが自身の中で認識されていなかったのか。 『心の闇』などという言葉は、「大衆」という今や正体不明の対象に対して発した、マスコミの言辞にしかすぎず、 なぜ私がそう言うかというと、だれしもが『心の闇』を抱えていると薄く認識しているのが現代だからである。 『心の闇』ということで言えば、それこそが近代から現代に至る(芸術)表現の主題である。 そしてまた、それに明確な輪郭を与える「科学」は、「確立」されていない。 人間は「心の闇」を抱えて生きている、というのは明治維新以来の『近代日本人』の植えつけられた観念である。 江戸時代であれば、自らの恥を雪いだ高潔な人物として理解されたのかもしれない。 そうした理解の多様な可能性を考えてみるときに、私たちは自分の都合のよいように、理解不能な出来事を位置づけていることが分かる。 不謹慎ではあるが、被害者の親が加害者の拘置先へ忍び込んで、加害者の寝首を掻けば、私たちは円満に納得するのではないかという気がしてならない。『忠臣蔵』である。 つまり、被害者とその肉親に同情しつつも、加害者を何らかの位置に置こうとする意識がある。 道真を恐れ殺しつつも、天神さんとして祀る心性が、ここにもあると言えそうな気がする。 |
||||||
| 04/09/15 | 殺人事件と、小山市での幼児誘拐殺人事件の、被害者の父親の言葉が相次いで報道された。 親と子が、ここまで癒着しているのかという感が強い。 では、お前は自分の子が殺されたらどうなのだと言われて、自分がどうなるのかはわからないのだが、なんだか異常な気がしてならない。 人が死ぬのは、つねに異常である。いったい何歳で死ねば、どのような死に方をすれば、正常というのだろうか。 殺されたのが子供だから、こんなふうに報道される。 そこに、私たちの免罪意識が働いてはいないか。 個人の感情を離れたところで、そう思う。 どこまで、いつまで、私は正義なのか? |
||||||
| 04/09/14 | 宅間守(40)の死刑が執行された。 下山明宏(39)が2児の殺害を認めた。 宅間の動機は今のところ整然とした説明が、本人からもその他からもされていない。 下山の動機は、報道によると学校の先輩が子連れで自宅に転がり込み、下山をないがしろにする行動を取ったということであり、覚醒剤反応が出たということだ。 子供を殺害すること自体に対する感想・反応は、許し難いということになるのだが、私の関心は彼らの、単純な論理・倫理性では理解しがたい心性である。 それを理解するためには、いったん同情的になり、また批判的になり、その振幅を経ねばならない。 単純な批判も同情も、何も語らない。 私は何を語ることができるのか? |
||||||
| 04/09/03 | 「人生の締め」考える 無職 N 62歳 先日の中国新聞で「人生の締めは自分らしく」という見出しの葬式に関する記事を読んだ。故人が生前に好きだった音楽で送る音楽葬や絵画、陶芸など趣味の品を並べて故人をしのぶ葬儀など、形式も多様化していると書いてあった。 2004年9月3日付「中国新聞」 『広場』欄 考えた。 |
||||||
| 04/08/08 |
|
||||||
| 04/07/24 | TVニュースを見ていると、白骨温泉の入浴剤「事件」や、デパートでの北海道物産展のニセ地元業者「事件」が、あたかも大事件のように取り上げられている。中には「危機管理」ということばを持ちだして、「正直に」「素早く」という原則まででっちあげて、重大さをでっちあげようとしている。 そんなに重大な事件なのか? 白濁した温泉を期待して来た客にとって、濁ってない湯を提供することと、どれほどの誠実さの差があるのか。 まして、デパートの物産展というのはお祭りの一種で、祭りの出店に本物を期待するのはおかどちがいではないか。 いちばんのインチキをしているのが、日本の現政府であるということを、国益ということばでごまかしていることを、さらに隠蔽しているのである。 温泉や物産展という非日常には、供給側と需要側の暗黙の了解という「インチキ」がそもそもあるもので、そんなことをことさらに何度も取り上げることには、何らかの意図があると見る必要がある。 真実を報道しているふりをしているTV会社が、「楽しくなければTVじゃない」と謳って二十ん時間TVを企画することに、矛盾はないのか。 私たちがTVを見て怒ったり笑ったりしているのは、すべてアミューズメントなのか? たぶんそうなのだろう。 小泉政権に対する私たち国民のスタンスも、そこから数ミリメートルも離れていないだろう。 民主党が議席数を自民党より上回ったところで、 自民党が大多数のブーイングを受けて実現できなかった消費税の導入を、細川政権がいともあっさりと実現し、なおかつ細川政権を新しい政治の誕生だと頬を上気させて語った人々のことを私は忘れない。 あの幻想のために支払った消費税は今や5%になり、いったい何億円、何兆円になっているのであろうか。 日本がいかにして大東亜戦争に突入していったのか、司馬遼太郎以下の世代は振り回されたという思いであろうが、当時選挙権を持っていた国民の多くが確信犯であったことを、ほとんどの者が知らない。知っている者は口をつぐんでいる。 日中戦争、太平洋戦争、二つの戦争で、日本の戦死者は、軍人・軍属210万人、一般市民300万人にのぼった。(この数字は、1940年日本人口7200万人の約7%となる。)(戦争論 日清戦争から太平洋戦争まで 日本は国連軍に参加するべきか による。このHPを引用したのは、Gooleでヒットしたというだけで、他意はない) 7%というのは、100人に7人。自分が93人の中の1人であれば、気になる数字ではないのだろうか。 きっとそうなのだろう。自分が死ななければ、他人の死というのは「悲しい事実」でしかない。 戦争というものは、そんなふうに起こっていたのだろうと、思う。それは、今も変わっていない。 |
||||||
| 04/07/13 | NHK-FM「日曜喫茶室」でゲストの永島敏行が東京オリンピック前後の子供の遊び場に言及したときに、道路がアスファルト舗装されていった自分自身の体験を思い出していた。 そしてそのあと、「山下達郎のサンデーソングブック」を聴いていて、ある発想を得た。 「連合国占領下の日本」 である。 過去の話ではなく、今もまだ、連合国占領下の日本であることを、私は認識する。 それは、政治的な話でも歴史学的な話でもなく、 アスファルトをはがすと、砂煙をあげる道があり、カーキ色の軍服を着た連合国軍のアメリカ人が、パルコの横の路地から、派手な私服で歩いてくる。 そう発想することから、私が今もくろんでいる詩集「私たちは生きているか」の立脚点が得られる。 映像としては、中学生の時に見つづけた影と光りの境界のあいまいさを、ローライフレックス・ミニ・デジで撮りたい。 |
||||||
| 04/07/13 | 政治について。 News23 多事争論 7月9日(金)「まつりごと(政)」 この15年間、選挙の度に投票前夜にいつも同じことを言い、同じことをここに書いてきました。「投票しましょう」ということですけれども、その間投票率はじりじり下がり続けて、無力感に襲われると同時に自分の言い方が説得力が無いんだと反省もいたします。 ということで、今日は違うことを言いたいと思いますが、政治の「政」という字は「まつりごと」とも読みます。つまり政治というのは元々はお祭りの部分を含んでいるわけであります。しかしながら祭りにも面白いのと面白くないのがあって、永田町でやっている祭りが面白くないのは確かであります。 しかし、面白い面白くないというものの言い方は別として、どちらかと言えば祭りを見ている人間の見方でありまして、祭りをやってみこしを担いでいる人は意外と面白いかもしれない、ということもあります。 阿波踊りに「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損、損」という言葉がありますけれども、いつも踊る人たちのことを「連」といいますけれども、政治という祭りが常連に占められてしまうと非常に歪んだことになります。祭りというものを面白くするかしないか、それはあなた次第だ、ということを改めて申し上げたいと思います。 (傍線ウエブマスター) 筑紫哲也はボケがその持ち味だが、そのボケにつっこむのではなく、「政治」ということばについて考えてみた。 とくに「政」(=「まつりごと」)について。 白川静は『字統』に次のように書いている。 【政】 声符は正。正は他邑を攻撃征服することを示す字。その支配のために攴撃(ぼくげき)を加えることを政という。正は征服、征は賦税、政が支配の形態を示す字である。 (中略) [論語、顔淵]に、「政なるものは正なり」というのは、儒家の理想論にすぎず、権力はつねに正であった。 【正】 正字は一と止に従う。一は口(い)、城廓で囲まれている邑(まち)。止はそれに向かって進撃する意で、その邑を征服することをいい、政の初文。正が多義化するに及んで、征の字が作られた。正はもと征服を意味し、その征服地から献納を徴することを征といい、重圧を加えてその義務負担を強制することを政という。そしてそのような行為を正当とし、正義とするに至る。(後略) なんのことはない、「政治」の「政」とは、力による強制のことである。 「権力はつねに正であった」の言は、このことを示唆している。学問の世界における権力による圧迫を一身に受け、はね返しつづけてきた白川静ならではの言葉であるなあ。 また、EXCEED英和辞典では、 pol�・i�・tics ━━ gov�・ern (傍線ウエブマスター) 漢字の「政」とほとんど、同じである。 一方、大辞林では、 まつりごと 0 【政】 〔祭り事の意〕 (1)領土・人民を統治すること。政治。政道。 「国の―を行う」 (2)神をまつること。祭祀(さいし)。 「尚侍(ないしのかみ)、宮づかへする人なくては、かの所の―しどけなく/源氏(行幸)」 さらに、 まつり 0 【祭(り)】 〔動詞「祭る」の連用形から〕 (1)神や祖先の霊をまつること。 (ア)祭祀(さいし)。祭儀。 「矢島氏の―を絶つに忍びぬと云ふを以て/渋江抽斎(鴎外)」「―をつかさどらむ者は天穂日命是なり/日本書紀(神代下訓)」 (イ)特に、毎年きまった日に人々が神社に集まって行う神をまつる儀式と、それにともなって催される神楽(かぐら)などの諸行事をいう。祭礼。おまつり。 「鎮守様の―」 (2)記念・祝賀・宣伝などのために催される行事。 「港―」「古本―」 (3)特に、京都賀茂神社の祭り。賀茂祭。葵祭(あおいまつり)。 「四月、―の頃いとをかし/枕草子 5」 (4)近世、江戸の二大祭り。日枝(ひえ)山王神社の祭りと神田明神の祭りをいう。 (5)情交。おまつり。〔俳句では夏の祭りを総称して祭りといい、春祭り・秋祭りと区別する。[季]夏〕 また、 まつりご・つ 【▽政つ】(動タ四) 〔「まつりごと」の動詞化〕 (1)政治をする。統治する。 「世をば、左大臣、仲忠の朝臣となむ、―・つべき/宇津保(国譲下)」 (2)とりはからう。世話をやく。 「家の事共―・ちてありければ/今昔 26」 みごとに「支配」、「強制」の意味が抜け落ちている。 今昔物語の時代から、政治家は「世話役」の意味が付せられているわけだ。 明治以降、とくに太平洋戦争敗戦以降、機構としての「政治」はヨーロッパ式になっているのだが、筑紫哲也風に(彼は日本古来の伝統にのっとっているだけなのだが)「政治」=「まつりごと」と言うことで、外見と中身が、呆れるほどの食いちがいを見せている。 ちなみに、『字統』では、 【祭】 肉と又とに従う。示は祭卓。その上に肉を供えて祭る。祭は人を祭り、祀(し)は巳(し)(蛇)に従うて、自然神を祀(まつ)るときの字である。廟中において祭るを察、祖霊の降臨を迎えて祭るを際という。 とあり、「政治」(=支配・強制)とはほとんど関連がない。 21世紀初頭の日本における政治の形態は、「まつりごと」ではなく「政治」であり、「politics」あるいは「govern」であることを深く強く認識することなくて、先はない。 しかしまあ、日本人はそのへんを曖昧にしながら「政治」を考えていくのであろう。 言葉の意味から考えるだけでも、この程度のことを言うことが可能であるのに、知識人といわれる人ですら何も考えていないことが明らかな「日本」は、このままおちゃらけて続いていくのだろう。 それはそれで正しい「日本」のあり方なので、わたしはこのままこの歴史の波に漂っていよう、と発言すればテロに遭うのだろうか? それほどの国であれば、まだしも。 |
||||||
| 04/07/21 | 追記 ちなみに、『字統』 【治】 声符は台(たい)。台に笞(ち)の声がある。台は耜(すき)の形であるム(し)に祝祷の器の形である口(さい;口の古字形)を加え、耜を清める儀礼。治は水を治める儀礼をいう字であろう。〔説文〕に川の名とするが、もと治水の義で、それより理治の意となり、官治・政治の意となった。 とある。 ただし、「政治」の語の初出はまだ調べていない。 「政事」の語については、 【政事総裁職】 1862年、内外の政務について将軍を補佐するために設けた職。初代総裁は松平慶永。 というのがあるのを思い出した。(大辞林) また、同じく大辞林に、 せいじようりゃく ―えうりやく 【政事要略】 平安時代の法制書。惟宗允亮(これむねことすけ)著。1002年頃成立。全一三〇巻中二五巻が現存。当時の制度・事例を広く集めて類別し、諸家の見解を掲げる。 とあるのを見いだした。 1002年ころから1862年ころまでは、「せいじ」は「政事」と記していたことが、高い確度で考えられる。 「政治」の用例や熟語から考えて、「政治」の語は明治以後かと推測される。 (もっとも、仮名書きしたとき「政治」は「せいぢ」である。) 「政」と「治」をくっつけたあたりに、王政復古にあたって神道を中軸に据えようとした意図が反映していて、たいへん興味深い。 もちろん調べのついていない憶測ではあるが、多分そうなのではないかという気がしてならない。 たまたま、「青空文庫」で石川啄木の『弓町より』から検索したが、「政治」という表記であった。ただし新字新仮名との注記があるあるため、さらに考証が必要。 漱石については、めぼしいところ数点調べたが「政」の字すらあまりヒットしない。(しかしそれにしても、漱石の作品を横書きで読むのは、未知の言語表記を読むような感じで、少しも目の中に入ってこない) それにしても、武力による制圧と治水の儀式をひとつにひっつけるあたり、まさに「和魂洋才」とでも言うべきであろうか。さらに巧妙というか、悪知恵というか、それまでにあった「政事」と発音がほとんど同じ熟語を作り上げているのである。 あ、作り上げたのかどうかは、未調査。 |
||||||
| 04/07/08 | あれこれ考えることはあるのだが、考えを発酵させる余裕がない。 体力がない。 手に取ったものを、ふいと取り落としたりする。 なんだかやばい気がする。 考えその1 携帯電話を財布にするという計画が着々と進み、もう実現しているそうだ。 そのリスクは、実際の財布を落としたときと同じだと、NTTの担当者が言ったそうだ。 財布を落としても、その中に手紙を入れている人はまれだろう。 不倫相手の携帯番号やメアドを入れている人も、まれだと思う。 論点がすり替わってないか? たとえば、顧客情報を、紙情報にして金庫に入れたときと、ディジタル化してLANに入れたときと、盗まれる可能性は、とか。 居酒屋でさんざん飲み食いして、いざ支払いというときに、電池が切れてたらどうなるんだろう? 大事故が起きて、何日も停電が続いたら、顧客情報はどうなるんだろう? 肝心の所が、抜け落ちた議論は、某国首相みたいだ。 考えその2 ネット社会とことばについて。 ことばが肉体から遊離することは、危険だ。 さまざまなことばの後ろには、肉体に裏付けられた感情があるはずだ。 感情とは肉体的反応で、人間の野生ですら、その肉体的反応を敏感に感じている。 そこがすっぽり抜け落ちたコミュニケーションに、何の意味があるのか。 このHPのような、BBSのような、チャットのようなコミュニケーションは、じつは活字コミュニケーションであり、活字コミュニケーションを操るためには、相当の熟練が必要なのだ。 2チャンネルをはじめとするBBSが、むき出しにされた感情の掃き溜めになっているのは、無理からぬ理由がある。 |
||||||
| 04/06/09 | 小学生の殺人事件が起き、人々はその理由を取り決めようとする事態が、再び起きた。 > 犯罪の原因を年齢や生活状況に片づけて、私たちは自分たちを正当化しているだけではないか。(03/10/04) 私は、容疑者はあの時被害者を殺さなければ容疑者自身が殺されると信じていたと、考えているが、それすら、私自身の安定を図ろうとしているだけだ。 報道されているような、チャットが原因ではないだろう。チャットがなければ起きなかったか。人が言葉によって追いこまれ、自身の存在が消されてしまうような危機感を持つことは、これまで、人間の歴史の中で何度か起こったことではないか。 神戸での殺人事件や、小学校への乱入殺人事件や、その見かけはこれまでになかったように見えても、その本質はこれまでもあったことなはずだ。 だからこそ、報道がなされる。 同じ状況におかれても、同じ事件が起きるとは限らない。それは、生育歴や、性格や、嗜好といったものが引き起こすものではない。 このように「異常に見える」事件に対して、私たちは割り切れなさややるせなさを感じるほかないのだろう。 そうでないのなら、中世ヨーロッパの魔女狩りや、狐憑きに対する態度と同じである。 魔女だから、狐が憑いていたから、という理由と、生育歴が、性格が、という理由と、じつは、理由づけ、それで納得することで自分を正当化するという点では、まったく同じだ。 教育従事者たちが生命の大切さを教え、社会倫理を叩き込もうと、こうしたことは起こってきたことだ。 人間はそう簡単ではない。それは(養老猛司ふうに言えば)人間は自然だから。 私には、事件の異常さより、被害者の親たちのその後の反応が、我がことのようによく理解できながらも、なんだか異常に感じられてならない。 人の死には、理由はない。 肉親を殺されて抱く憎悪の念にも、その理由はない。憎いから憎い、それで充分だろう。 憎悪の悪循環を防ぐために、刑法があったり、あるいはかつては仇討ちという「法」があったのだろう。 私たちはこうした事件を前にして、さまざまな理解を試みる。心理学的に、行動学的に、社会学的に、さまざまに理解を試みても、それは理解にしかすぎず、理解とは理解を試みる者の心の安定でしかない。 どんなことをしても、こうした事件がなくならないことが、その証明なのかもしれない。 そして、そうした訳のわからなさをかかえていることが、私たちの健全さの証明なのかもしれない。 私たちが私たちの思うように存在するのなら、私たちがこの世に存在する意味はないような気がする。 死を悼み、その死を理由づけ、しかしそれは、生き残った者の自己満足であることを知らなければ、本当の意味で、死者や死をもたらした者を理解したことにはならない。 報道とは、覗き見であり、野次馬根性であることを、(報道関係者は知らなくてもいいが)報道の受容者は知っておかなくては、全員が報道関係者になり、評論家になってしまい、死や、死をもたらすことのほんとうの意味が幽霊のように宙をさまよう。 |
||||||
| 04/05/28 | 「夜空ノムコウ」(作詞:スガシカオ 作曲:川村結花 唄:川村結花)を久しぶりに聞いた。 ポップスは今自分が踏みしめた足を少し持ち上げて、見つめた足跡を見つめ、クラシックはその足跡の続いてきたうしろと、これから続いていく先を見つめる、というふうに考えた。 ここでいうクラシックとは、曽我部清典の音楽を基準にしている。というか言うまでもなく、そういう基準に今の音楽はジャンルわけされている。 そう考えると、「夜空ノムコウ」は、したたかに、「今」しか見ていない。 「今」の中にある「過去」と「未来」をえがいている歌のように聞こえてくる。 そんなことで、SFチックに聞こえたりするのだろう。 表現というのは自分の「現実」の中にあるものでしかなく、現実というものは、「今」がポコッとふくらんでその左右に玉子のカラザのように過去と未来が細々とくっついていて、でもしがみつくものはその細いカラザしかなくて。 じつはそのカラザの細さやしぶとさが表現を支える唯一のものである。 たぶんその点を、嵐山光三郎も書き得ていない。ような気配がある。(「芭蕉紀行」)まあ、死ぬことを前提に書かれた文章だから気に留めるほどのこともないのかもしれない。 調和的な結論を言えば、「ポップス」と「クラシック」の差は、カラザを唯一のものとしているかどうかで、演奏する音楽の差異の中にはないものである。 曽我部清典がポップスで、モー娘。がクラシックであるのは、当然なのかもしれないが、そうとは聞かない人が案外多いということは、矢沢永吉とともさかりえが同質に先鋭的であることが理解されないことと等質なことであろう。(む〜ん。難しい言い方をすると、自分がえらそうなこと言ったような気がする) とりあえず、今日はねむる。 |
||||||
| 04/04/14 | (人間の)存在意義の差異は、意識の中にしかない。 だから、意識の中を旅しない者には、世界中のどこに行っても、そこはいつもとはちょっと違う自分の場所でしかないし、意識の中を旅する者にとっては、いつもと同じ場所が突然に見知らぬ土地として表れたりする。 2月のある日、昼食にでかけた町角の信号待ちで、煉瓦色の舗道に差す日射しを、カイロの日射しと感じたのは、なんだったのだろう。 なにかの機会があれば、私は海外に旅するだろう。あるいは「ボーダー」(原作:狩撫麻礼、漫画;たなか亜希夫)の主人公のようにアジアの東から西へと旅することもあろう。 しかし、それは「ちょっとちがうここ」なのかもしれない。そうではなく、まったく違うどこかなのかもしれない。 意識の差異の中で自己を認識している私たちのあいだで、ただひとつ共通することといえば、 私たちは生きている ということしかない。 生物的・物質的に存在しているという、その中にしか、私たちの共通点はない。 意識の共通点をさぐっても、それは虚しいことにすぎないだろう。 私たちは生きている。 たとえどのような異なった意識を持っていても、生物として、物質としての存在であることは、どのようにも否めない事実として認識されることではないか。 イエスが死者のことは死者にまかせよと言い、シャカが解脱を説いたのも、生きているという否定できない事実に基づいてではなかっただろうか。 2004年現在、イラクの人々が世界中につきつけようとしていることもまた、その事実だけなのではないだろうか。 「私たちは生きているか?」という私の個人的問いかけは、こうした認識の中でしか意味を持たない。 |
||||||
| 04/03/30 | 「ユビキタス」とPC。 私はどうしても、PCのPにこだわってしまう。 パソコンがここまで普及したのは、Pつまり、パーソナルであったからだし、パーソナルを追求してパソコンは発達してきた面が強い。 それは、道具というものが便利さを追求して発達し、その便利さの尺度は、その道具を使う個人の身体の拡張ということにおかれてきたからである。 ネットワーク社会をむかえて、私たちは、自分の身体が地球の大きさにまで拡張されたのである。 それを称して、グローバル化とか言っているわけだ。 そして「ユビキタス」。グローバル化にまで至った身体のPCにおける拡張性の障害が、ワイヤーであった。 その意味で、Pentiumが唱えている「Unwire」は象徴的なわけだ。wirelessでなくunwireとは、私たちの身体の本来的特性なわけだから。 ユビキタスとプライバシーの関係は、私たちが道具という身体の拡張を求めたときから内包されていた問題なのである。 身体の拡張の行き着く先は、肉体の統括機能である脳にいたり、脳の拡張を担った道具がPCなのである。 単純に言って、私たちのひとりひとりが地球規模に拡張されたら、地球はパンクするということである。 「ユビキタス」の矛盾はこうして露呈してくる。 そして、その矛盾が「プライバシーの保護」といったありきたりの方法論ではおさまらないだろうことは、あきらかだ。 「個人」の概念すら変革することを求められるときがすぐそこに来ている。 が、じっさい、「個人」の認識は最終的には肉体に求められるのだから、 私たちが肉体を放棄するか、PCネットワークが破綻することすらできない混沌から抜け出せなくなるか、あるいはその両方であるか、行き着く先はそこしかない。 言葉の指し示す本来的意味を踏み外さなければ、この程度のことは自明の理なのである。 それを便利さとか、新しい世界であるかのような言辞を弄しなければならない状況を、閉塞状況であると認識できないほどに、私たちは言語から遠ざかっているのだろうか。 |
||||||
| 04/03/09 | 関川夏央『豪雨の前兆』を読み終えたのは、急性虫垂炎の手術を終えた後のはずだが、2月25日だったろうか。その日は手術の翌日なので、26日なのかもしれない。 いずれにせよ、46歳の誕生日を、だれもいない病床でむかえ、バースディ・ケーキの代わりに、私は重湯と、味噌汁ともポタージュともつかないスープと、濃厚な味のリンゴジュースを飲んだ。 腹を切ってから2週間後、私たちには「明治維新コンプレックス」とでもいうべきものがあるのではないかと、思いあたった。 コンプレックス=劣等感でなく、錯綜した感情という意味での。 でなければ、100年以上昔のことを、こんなに気にすることはないだろう。 明治を、そして明治から続く日々を、人々はどのように過ごしたか、なぜ私たちは気にするのだろう。 あるいは、明治以前の人々がどのように日々を過ごしたか。 私たちは、私たちが選び取ることのできた選択肢のもう一方を、そうした思考の中から想像してみようとしている。 司馬遼太郎を読むことも、藤沢周平を読むことも、あるいは吉村昭を読むことも、私たちが選ばなかった選択肢の行く末を惜しむことなのかもしれない。 徳川幕府が瓦解しなくとも、政体は現在のようであったろうことは、確かなことだろう。 徳川家一家で日本を支えることは不可能になっており、いずれは天皇という概念を中心に据えなければ、たちゆかなかったであろう。 天皇という概念を中心に据えた政体を実現するのが、薩摩・長州の「田舎っぺ」であるのか、徳川という洗練された(?)存在であるのか、「田舎っぺ」である私にとっては、大差ないように思える。 いずれの道を選んだにせよ、私の暮らしている21世紀の日本は、今のようになるしかなかったように思えてならない。 明治維新後、さまざまな選択肢があり、その選択肢の向こう側にさまざまな世界があるように見えるが、日本という国土や文化の中に存在している日本人という存在は、今のありようにしかたどり着けなかったのだろうと、思う。 そんなふうに、私は関川夏央や司馬遼太郎や吉村昭を、読んできたのかもしれないと、気づいた。 |
||||||
| 04/01/31 | 鴎外『舞姫』と漱石『こころ』の共通点について 「豊太郎」=鴎外。「エリス」=「豊太郎(=鴎外)」が棄てた女。 |
||||||
| 04/01/24 | 一例として、コインが草むらに墜ちた音。 それを録音して増幅すれば、暴力的な音になる。 それは、その音自体が内在していた力なのか。増幅する過程(イフェクターとかアンプとか)が持っている力なのか。 力のないものをいくら増幅しても力は外在化しないだろう。 しかし、増幅してはじめて外在化する力もある。 微弱なものの持つ潜在的な力。 そんなことを、Phewと坂本龍一のコラボレーションの音から、考えた。 |
||||||
| 04/01/07 | 二日前から、目に見える景色が言葉として見えている。
この暮れから新しい詩集を書いているからだろうか。 この世界はすべて、言葉でできあがっているようにしか目に映らない。 これはつまり、私たちは世界を言葉でのみ理解していることなのだろうか。 分析はともかく、そのように今の私は見ているということを、書き記しておく。 |
||||||
| 03/12/24 | 22日の坂田明ライブはよかった。 そこで考えたこと二つ。 なぜ自分が、中学生の頃から現代音楽を好んでいたのか。 結論から言えば、それが「真実」を写しているから。 ロマン派(前期)のような音楽は、そんなに調和がとれて終始一貫しているのが世の中ではないという感想を与える。 とらえどころのなさ、理解の拒絶あるいは理解の多様性、そうしたものが、私にとっての世の中なのだ。 「ハタハタ」を聴いていて、冷たい海の中を群れで泳ぐ魚の姿が浮かんできた。 それは「かわいそう」という金子みすずのとらえ方とはちがった、人間には理解できない魚の世界が描かれていた。 いや、あるいは、同じなのかもしれない。 が、いずれにしても、理解不能のものを、とことん理解を試み、それでも理解不能なところを理解不能として理解する。 そんなところが、金子みすずとはちがっている。金子みすずも、夭折しなければ、そんな地点に到達したのかもしれないが。 |
||||||
| 03/12/12 | ふたたびシッダルータについて。 「脳はバーチャルリアリティを目指す」という、養老猛司の言が納得できる。というより、納得できると言うことは、自分の中にある物を示されたと言うこと。その意味で、私は養老猛司の「信徒」ではないし、「信徒」である。(これについては、いずれ説明が必要か? まあ、いいや) 人間は(その脳の外見のとおり)小脳や間脳を大脳が押し隠そうとしてきた。日高敏隆/竹内久美子の言葉を借りれば「ワニの脳」を押し遣ろうとしてきた。言い方を変えれば、理性が情動を管理しようとしてきた。ロゴスのパトスへの優位性。 宗教は、そのために大きく機能してきたと言えるのではないか。大きく肥大した大脳が、小脳・間脳に対する優位性を確保するために。 養老猛司的に言えば、それが「人間の脳の癖」なのだろうけど。 シッダルータは、まさにその脳の癖に従って行動をつづけた。 支配者の一族として奢侈に耽ることも、肉体を痛めつける極端な行(ぎょう)も、大脳が己の優位性を確定するためのものであったのだろう。 そしてスジャータのミルク粥が彼に示したものは、肥大した大脳と小脳・間脳のバランスをとることだったのではないか。 いや、バランスという言葉自体が大脳にかたむいている。 大脳/小脳・間脳も、人間の生存にとっては真実だということに行き着いたということだという気がする。 ひとつの神=真理を想定することは、大脳にとって容易いことだが、それは人間という生存にとっての真実ではないと、モリナガさんとの茶飲み話から思った。 |
||||||
| 03/12/08 | > ミクロを見つめることでマクロへ到達でき、それはまた別のミクロへと敷衍できる。 > 私の「詩」は、そのような詩になり得るのだろうか。 ミクロを見つめるとは、言葉を見つめることだと、気づいた。 言葉の運動を見つめること。それがミクロ。 植物について書くとか、存在について書くとか、それらはすべて「話題」であり「主題」ではない。 私の詩の主題は「言葉」でしかない。 言葉によって何かを表すのではなく、言葉自体を表す、そこにしか私の詩はない。 たぶん、すべての作家・詩人の命題は、そこにしかないと思う。 金子みすず論を試みている今、そこを外すことの危険性を感じている。 |
||||||
| 03/12/06 | そういえば、先週の日曜日、女性の耳が、漫画のエルフみたいにとんがって見えた。 「ゆらゆら」の食堂の女の子だけかと思ったが、エルフの耳を持っている女性と普通の耳の女性とがいるのだった。 二日くらいそう見えていた。 どうもおかしくなっている。 |
||||||
| 03/12/05 | 今日午後3時過ぎ頃から、女性が女臭く感じられ始めた。生臭いというか。男性はどうかというと、職場には数えるほどしか男性がいないのだが、たぶん、やはり男臭いのかもしれない。 帰り、ゴルゴンゾーラ、イタリア産生ハムや、ワインを買って、5000円以上払ったが、その時はそれほど感じなかった。明日どうなるかわからない。 さて、中村とうようが「ポピュラー音楽の世紀」で、個人的技巧の世界に奔ったために、ジャズはポピュラー音楽とは言えないとする中で、カリブ音楽への接近を試みたチャーリー・パーカーに、ジャズがポピュラー音楽になる可能性を見いだしていたが、 チャーリー・パーカーの音楽は明るい、と「Bird Symbol」を聴いていて気づいた。破滅的・悲劇的最期を遂げたのだが、パーカーの音楽は、それ以前にもそれ以降のジャズにもないくらいに、明るい。 ひょっとしたら、パーカーの希有の才能の本当のところは、複雑なフレージングなどではなく、その明るさにあるのではないか。 コルトレーンが、お茶目でキュートな「My Favorite Things」をやると哲学的・求道的になるのと対極的に。 麻薬に溺れ、アルコール漬けになって30代で死んだのは悲劇的な話だが、それと個人の人間性は関係がない。音楽家個人の人生と、その作品を結びつけて理解することは、たやすいことだが、大きな誤解に結びつきやすい。 パーカーは、演奏中はハッピーだったにちがいない。 |
||||||
| 03/11/25 | 宗教に関する話になる。 一昨日あたりから、シッダルータの苦行の果てにミルク粥を与えたスジャータのことが心にかかっている。 シッダルータ(後のブッダ)は、現在のネパール南部に生まれ王子として何不自由ない生活を送ったといわれる。そして29歳の時に、息子ラーフラ(「蝕」の意らしい)の誕生直後に出家した。(「出家」というのは後の仏教の方便で、「家出」と同じだな。) 要するに「満ち足りない思いだった」。(としか言いようがない、と思うのだけど) 当時の29歳といえば、充分な歳であり、もはや老境の入り口と言ってもいいかもしれない。(たぶん、21世紀の今の私くらいの年齢感だと思う) うーん、好きなだけ好きなことをして、後は死への準備をしようかというときに第一子の誕生。ラフーラ(蝕み)という名をつけようというのもわかる気がする。 その後彼は6年にわたる苦行に入る。苦行その他についてはここを参照 まあ、とことん肉体と、肉体に関わる感覚を苛め抜いたわけだ。たんなる断食とか、そういうのが綺麗事に思える苦行だ。自分の糞尿のみならず牛の糞までも喰らったという。 うーん、なかなか結論に行きつかない。 言いたいことがふたつある。 ひとつめは、「愛欲」のこと。もうひとつは、「肉体」と「霊魂」の二元論。 私は今、「愛欲」(言葉本来の意味で。執着とか、妄執とか)のまっただ中にいる。その「愛欲」から離れようとしたときに、シッダルータは苦行という方法をとり、6年の末ほとんど失敗しようとした。 たぶん、私も彼のように(物質的に?)余裕があるなら、その方法をとったと思う。小さな田舎の寺の寺男にでもなりたいと、考えたこともある。 しかし、彼はその方法に失敗した。失敗した彼の前に現れたのが、ミルク粥を持ったスジャータだった。 そしてその49日後にシッダルータは悟りに達するのだが、私にはその時の彼の見たものがわかる気がする。 心が迷うとき、私たちはそれを「肉欲」だと定義づける。そしてじっさいに、肉体が弱ったとき、私は妄執にとりつかれる。そしてそれは、必要なだけの食事を摂れば(一時しのぎかもしれないが)、自分を強く保てる。シッダルータは、肉体を極限に削ぎ落とすことで、かえって肉体の「欲」に蝕まれたのではないか。 「愛欲」を極限に達成することも、また極限に削減することも、少女スジャータがシッダルータに与えた一杯のミルク粥に如かなかった。そしてシッダルータは、ミルク粥にも、スジャータという少女にも、最大の「愛欲」を見出していただろうと、私は(かなりの確度で)思う。 肉体と霊魂の調和と、多くの宗教者、哲学者は言うだろうが、私は、霊魂は「存在」しないという立場なので、間脳と大脳が葛藤の末、大脳がその妥協点を見出したと言おうか。 たぶんあれだけの苦行の後であれば、性欲も味覚欲も、その妥協点が極限に下がっていたであろう。たぶん、私の感覚からすれば、肉体が明日の朝まで保てるだけの充足があれば、私たちは間脳と大脳の妥協点を得られるのではなかろうか。 もちろん、日常的なサイクルでそれを繰り返すのでであれば、毎日葛藤せねばならず、その毎日の葛藤が煩悩というものかもしれない。が、それはそれでいいのかもしれない。 シッダルータの偉大な点は、「肉体」vs「霊魂」の二元論を見いだした末に、それを克服した点にあるように思える。彼はその後45年間、自分の発見したものを説いてまわったという。 |
||||||
| 03/11/09 | リアリティーがない。と養老猛司がTVで言っている。現代社会のありようについてだ。 昨日、職場の廊下を歩きながら、「意識が歩いている」と私は思った。 養老猛司の講演の話を聞いていると、千日回峯を成し遂げた阿闍梨が、植物や景色の見え方が違うという話しかしなかったこととよく似ている。 名もない中間僧が、墓場の死体を毎夜眺めて声を上げて泣いたことによって悟りの境地に近づいたという話とも、よく似ている。 さて、肉体が疲れると「意識が歩いている」という「実感」が生まれる。 その時の「意識」とは何かというと、勝手に歩いている肉体であり、肉体を歩かせている脳の働きなのであろう。 私たちが「自分の」意識だと主体的に思っていることというのは、たかだかそういうことなのだと思う。 たかだかそういう自分を、見つめることが、私をみちびいてくれる。 そういった詩を書きたい。 |
||||||
| 03/10/28 | 生きることの本来的意味は、不随的機能によって担われている。 (養老猛司的に言えば)私たちの脳が、脳自らの滅びを否定するがゆえに、脳の自己認識としての「魂」や「永遠の命」を仮想する。 しかし、私たちは小脳や視床下部が死ねば、死ぬのである。 大脳の死を死とするのは、「脳のわがまま」。正確に言えば、私たちの肥大した大脳のわがまま、なのである。 私たちは、自分の存在の中に、ゴキブリや、その他の嫌悪している生き物をかかえているのであるのに。 人間に飼われているネコは、自分がネコであるよりニンゲンであることで自分を認識しているようである。そして、彼らは、ニンゲンよりいっそう小脳や視床下部で自己認識をしているがゆえに、自分が滅びていく存在であることを、かぼそく堪えているように思える。 |
||||||
| 03/10/15 | 「Gaia Symphony」、予告編を見たが、「永遠」とか、「魂」とか「一つ」とか出た時点で、だめだ。 人が何を感じようがそれはかまわないが、みんなもそう思おうよ、てなスタンスが私にはだめだ。 そんなこと当たり前じゃないか。そして、そんなこと、みんなわかってるよ。さも、この映画はわかってない人をわからせるために作った、って感じがイヤだ。見る人間を馬鹿にしている。 私たちは「永遠」であり、「一つ」の「魂」の存在であるというカテゴリーの中で喜怒哀楽の全てを行っている。それはレベルの問題ではなく、それを口にしたところで、何も解決しないというところで私たちは生きているのではないか? 解決を棚上げにして、認識のレベルを上げるところが、インチキ宗教っぽい。 私は、私の日常の中に、宇宙を見る。全存在の統一を見る。そしてそれは、私の私的なレベルであるからこそ、私にとって意味を持ち、私にとって意味を持つからこそ他人へと伝えられる。 私は、これまでも、これからも、そういう地点から詩を書き、写真を撮り続ける。 徹底的にミクロにこだわることで(ミクロにこだわることしかできないのだが)、マクロに到達するというのが、私の変わらぬスタンス。 |
||||||
| 03/10/04 | 17歳は少年か? と、自分の17歳の時を思い出した。 まあ、考えていることや、することは大人ではなかったのかもしれないが、世間から大人といわれるこの歳になって、何が変わったか? マスコミで少年犯罪をうんぬんしている人たちが、自分が大人だという意識を持っているのだろうか? 大人の定義とは何? 自分の寄って立つところを明らかにしないまま、生きてきた時間の長さによって他人を区切り、論評することは、思考を放棄した、予定調和の中に生きていることを正当化しているだけではないか? 吉村昭が犯罪について述べていた、年齢や、生活状況や、そういったものに一元的に還元できない、といった見方が、本当のところのはずだ。 犯罪を犯さないものが圧倒的に多数であるこの世界で、犯罪の原因を年齢や生活状況に片づけて、私たちは自分たちを正当化しているだけではないか。 年齢によって犯罪を犯すわけではない。それならば、17歳の時の私は何らかの犯罪を犯した、あるいは犯しかけたはずだ。 池田小学校事件の宅間被告に対して、私たちは有効な批判の言葉を見出していないにかかわらず、長崎の少年殺人犯に対しては、少年犯罪という枠組みをあてはめて批判を試みる。 年齢は、単に、犯罪に対する私たちの批判の隠れミノになっているに過ぎないのではなかろうか。 「大人」をどうすることもできないのに、「少年」をなんとかできるはずはないではないか。 |
||||||
| 03/10/01 | 勤め先のバンドでやるために、Weather Reportを聴いている。 夏の旅の時はJaco Pastorius Big Bandの「Twins」を聴いていたし、やはりJacoのベースの凄みから離れられない。 地獄の淵を覗いた、と言うか、それより「天国の淵を覗き込んだ」という方が当たっているような、そんな音楽が満ちあふれている。 ここまで来ると、どんな音を出しても満足できないのだろうなという、響きがする。 Jacoは過去のベーシストのほとんどを(唯一スコット・ラファロをのぞき)けなし、ベースギターでピアノのような演奏をしようとした。そして、それはほとんどなされた。 そんな希有のことがなせたのは、彼の耳の奥には、天国の音が鳴っていたからにちがいない。 しかし、天国の音は、この世の実際の音としては存在しない。(あり得ても、ほんの一瞬の幻のようなものだろう) このジレンマがJacoを駆り立て、焦燥に陥れた。喧嘩っ早かったのも、わかる気がする。 私には、彼の演奏がそのようなものとして聞こえる。 天国の淵を覗き込んだ者にとって、この世は地獄なのだろうか。 Jacoのエッジの立った演奏から、そのようなことを考える。 |
||||||
| 03/09/30 | 坪内祐三『一九七二』昨晩読了。 1972年が個人的に特別な意味を持っていると感じることは、私にもある。著者と同年生まれ(たぶん私が早生まれで一級上)であるし、1972年には特別の意味があると、私自身も感じていた。 たとえば、Chicagoの「Chicago V」、Yesの「Close To The Edge」やマイルスの「On The Corner」がこの年の作品。 その他、T.レックス: ザ・スライダー、サンタナ: キャラバン・サライ、ディープ・パープル: マシン・ヘッド、デビッド・ボウイー: ジギー・スターダスト、トッド・ラングレン: サムシング/エニイシング、ニール・ヤング: ハーヴェスト等々。 今の私の音楽的嗜好からして、この年の作品の多くが、好悪混ぜて発表された年だ。 世界的に何があったか。一言で言えば、「売れ線」ロックがスタートした年であろう。 そういう意味で、中央都市でこの年を過ごした著者と、地方都市のぼんやりした私の差があるわけだが。 それはともかく、「情報を消費する」とはなんだろう? 何となくならわかるのだが、きちんと説明せよと言われると、できない。 消費の対義語は、生産。 たしかに、1972年当時は、今と比べれば、個人のもとに届く情報の量はかなり少なかった。 だから、人々は「情報を生産」していたのか? 言葉の意味がわからない。この言葉は、著者だけでなく、たぶん80年代から言われ続けていたことだろうと思う。 しかし、きちんとこの言葉と向かい合おうとすると、???????? さて、「情報化社会」とは、その主語や目的語があきらかでないということで、「キレル」とか「ムカツク」と同趣の言葉である。 そして、よくわかんない言葉だけに、この時代を生きる私たちの意識を反映している、あるいは、意識そのものと言える。 つまり、私たち自身が情報である、と白状している言葉なのではないか。 そしてそれは、事実でないだけに、私たちの指向を如実にあらわしている。 つまり、私という存在は情報以外の何ものでもない、という指向(=認識/希望)。 西暦2003年現在、私の周りに起こっている事件や、その論評のほとんどが、こうした基本(=無意識)認識の上に成り立っている。(かのように思える) 情報としての認識が、ようやくなされた時代なのかもしれない。 情報とは、それを手に入れた者にとっては、全て等価である。つまり、手に入れるということにおいて等価である。 情報化社会とは、そこで止まる社会のことである。 情報を手に入れて何をするかというと、情報に手を入れて新しい情報(=別の情報)らしくして送り出す(=陳列する)ことである。 私は、その向こうが知りたい。 茹卵の薄皮のような「情報化社会」の、その薄皮を剥いた時に、どのような白身の表面があらわれ、さらにその奥に、どのような黄身があるのか。 「情報」とは、殻を剥いていない茹卵のようなものだ。 そして、茹卵で一番美味しいのは黄身であるし、白身との取り合わせによってさらに味が生まれる。 しかし、私たちは薄皮を剥くこともできなければ、殻を上手く割ることすらしていない。 評論家や研究者でない私は、それを詩においてやろうと、思っている。 |
||||||
| 03/09/24 | 最近鬱病がよく取り上げられている。鬱病を克服すれば、自殺から逃れられると。 これでまた、私たちは死という神秘から、もう一歩遠ざけられるのだろうか。 こうして得た生に、意味があったとしても、どういう価値があるのだろうか。 三島由紀夫が、生よりも意味のある死と言い、NSPが「この世で一番大事なものは 一体何だろう 金でもない勉強でもない まして女じゃないさ もちろんそれだって 少しは大切だけれど もっと大事なことが 絶対あるはずさ」(「あせ」)と歌って、安易に「生きること」という解答を回避した、その深遠さはどこに行ったのだろう。 生きてりゃいいもんじゃないだろうと、言うことは、はたして能天気なことなのだろうか。 沖縄人の言う「ヌチドゥタカラ」と、やまとんちゅの言う「命が大事」との差のなかに、大きな隔たりがあるような気がしてならない。 命は大事だが、命を大事にすることだけが大目的になっていていいのだろうか。 その命を使って何をするか。 それが家族を愛することであるのなら、はっきりと、「団塊の世代」の生き残りたちの、生き残りゆえのあまりに低劣な限界が露呈しているのではないか。 家族を愛するとは、家族のために生き残ることではあるまい。それは、死を回避する言い訳にしか聞こえてこない。 死を回避することがアプリオリに善とされることによって、今の私の周囲の世界の病理が見えてくるような気がする。 人に死を薦めることは、私はしないが、死もまた自分の生の一部であると思うならば、死を回避することのみが、生の全てではあるまいと思う。 ゴキブリを絶滅させようとしながらも、絶滅危惧種をなんとかしようとするのと同じ矛盾があるように思える。 ゴキブリが残り数匹になった時に、私たちはゴキブリを絶滅危惧種として保護するのだろうか。 |
||||||
| 03/08/27 | NHK・ETVスペシャル「さまよえる戦争画・従軍画家と遺族たちの証言」で、肝心のことを回避しているようであったが、最後に従軍画家の遺族の一人が、「絵として評価を受ければいい」というようなことを言っていた。その他の遺族は、混乱、あるいは混乱を糊塗する耳触りのよい考えを自分の生き方としている。 (もちろん、編集の際に、重要なことが削除されたのかもしれないが) 問題は簡単だ。 ショスタコビッチの作品が、崩壊した共産主義の政策下で作られたから、価値がある/価値がない、という問題なのか。ということと同じだ。 テキスチュアの問題とサブジェクトの問題が、混同されている=明瞭に分離されていない、あるいは、サブジェクトのテキスチュアにもたらす効果を、考えないようにしている。 吉本隆明が「言語にとって美とは何か」で最初に置いた明瞭な立脚点が、みごとに無視されている。あるいは学習されていない。 それらの作品を、絵としてみたときに、彼らの戦後の作品と比して、どちらが優れているかが看過されている。 戦争画が、技法的には当時の各画家の技法のぎりぎりの点で描かれながら、絵として物足りなさを感じさせ、かといって彼らの戦後の作品と比較したときに、何かしらの充実を持っている。さらに、戦争画を描いたことを負い目として持っている画家の戦後の作品のなにかしらの甘さ、とは何か。 チャイコフスキーの「序曲1812 年」は、帝国主義的ナポレオンの侵攻を防いだことを描いているから優れているのか。フルトベングラーはナチスの前で指揮をしたから、その音楽は否定されるのか。 全てはその時代に利用されて評価されるのなら、従軍画家たちの作品は、戦中も今も単に利用されているばかりで、芸術(art=技)としての評価がなされていないということになるのだろうか。 03/08/16 (追記) 光太郎や、達治たちの戦争詩の評価は、どうなされているのだろうか。吉本隆明の文章しか読んでいないのだが。 |
||||||
| 03/07/15 | タイで、肥満児童が問題になっているという報道がNHKでなされた。 人間も動物であるならば、いくらかの飢餓状態が常態であって、食物が摂取されたときそれを蓄えるように身体ができあがっていることは、疑いのない、そしてしようのない事実であろう。 飢餓→飢餓のない世界→肥満からの逃避 この図式は、じつは「人間は動物ではなく、理性の存在である」という認識(あるいは希望)によって、貫かれている。 大きな振り子の振幅のように見えるこの事柄は、「人間は動物ではない」という妄信によってつくりだされた。 ほんとうに私たちが「理性の存在」であるならば、「人間は動物である」ことを理性の中に組み込んでもよい時期はとっくに来ているはずなのに。 それは西暦1980年になる前に到来していたはずだ。 それでも、私たち「先進国(=食料過密地域)」の住人は、「食料過疎地域(=後進国)」から何も学ぼうともせずに、飢餓を撲滅しようとしている。 それが、私たちのヒューマニズムなのか? 一方的な流通ではなく、相互流通の中から、私たちに見えることがあるのは、とっくに理解済みの事項ではなかったのか? |
||||||
子供であることが許されない子供の世界。 子供の権利条約が結ばれたとき、 今回の長崎幼児殺害事件、 オウム事件裁判での土谷正実への死刑求刑。 テレビの世界、 都市化(=脳化)、 「子供の権利条約」(一九八九年に国連で採択)について、日の当たる大通りを歩く賛成論者と、日陰の裏通りでたむろする反対論者が輩出されたが、私が思ったことは別のことだった。 権利を認めることは、認める側が、認められる側を、認められる側の承認なしに、認める側に取り込むということ。 子供には子供の聖なる領域があることは、柳田国男の論考にも見えることだが、もし私が1989年当時子供であったなら(心や、自分のつもりとしては、子供だったが)、当惑、あるいは迷惑を感じただろうと、その時思っていた。 権利を認めることは、認める側が、認められる側を、認められる側の承認なしに、認める側に取り込むということ。 この論点での論考は、あまりなされていないのではないか。わずかになされていたようにも思えるが、主立った議論にはならなかったように思う。 もちろん、当時の子供たちの置かれた状況というものが、あまりに悲惨である地域があった。そしてその地域の子供たちを守るためになされた決議であることは、論を待たない。 しかし、権利を認めるという言語の中に、子供というカテゴリーを大人というカテゴリーの中に取り込んでしまったことを、どう考えるか。 その結果、どういうことが起きてきたか。私は考えてみたい。 「大人」概念の曖昧化。 子供犯罪の「見かけの」増加。 「大人」の権利と「子供」の権利の同等化による、「大人」の「子供」化。 「大人」は「子供」を産むことはできるが、「子供」は「大人」を産むことはできないという、単純な理屈の喪失。 「香港で今月に入って3度目の大規模集会があり、2万人以上が参加、『我々はより良い政府に値する』として、董建華・行政長官の辞任と自ら指導者を選ぶ権利を求めた。」 |
|||||||
| 03/07/08 | 何となくケーブルテレビを見ていると、96年オリンピックのバスケットボール、アメリカ・ドリームチームの番組をやっていた。 プロがアマチュアスポーツの祭典に堂々と出ることは何を意味するか。 プロスポーツが、見せ物から脱却したこと。 もちろん、有力なアマチュアがすぐにプロに流れるというアメリカ合衆国独自の事情があったわけだが、音楽にせよ、スポーツにせよ、他人様の前でそれを見せて、お金をいただくというのは「見せ物」(言葉の正確(原初的)な意味で)であるわけで、それがプロであったところから、かなり離れてきたわけだ。 それは、音楽でも、芸能でもその傾向はますます強くなっている。 そのこと自体は、職業の貴賤が無くなる傾向にあると考えれば、正しい傾向だし、ドイツでは物作りの職人も、音楽家も、最高位はマイスターと呼ばれることを考えれば、正当なことだ。 そもそも、ヨーロッパではスポーツ自体が貴族のものであり、下層階級者より知能的にも肉体的にも優れているものが貴族たるゆえんであった。 日本においても、それらは、「芸」であり「術」と呼ばれている。武道でさえ、「武術」と呼ばれるではないか。 それは、農業や漁業といった第1次産業とは違う、まさに「術」の世界である。 別段崇高なるものでもないし、また卑下する対象でもない。第1次産業には「術」は通用しない。しいていえば、「技」はあるだろう。父方の家系の漁業を見れば、確かに「技」はあるように思える。しかし、「術」は通用しない、通用しようがない。 こう見てくると、日本語の「術」と「技」の使い分けはじつに厳密である。「芸術」だけでなく、「忍術」、さらには、「手術」まである。 芸術賞を授与することが伝えられたときに、「私は芸は使っても、術は使いません」と言ったという話が、ある落語家の伝説としてある。 「術」とは目眩ましであり、「芸」とは修練だと、そこには厳然たる峻別がある。 「手術」と「手芸」では大違いだ。どちらも手を使う技術には違いない。手芸では誰にも理解できる着物ができるが、手術となると、浮き世の誰もが理解できない不可解なことが起こる。 同じことは「話芸」と「話術」の関係でも言える。「話芸」は理解の上に成り立ち、「話術」は不可解の上に成り立つ。「武芸」と「武術」でも同じ。 「陶芸」はあるが「陶術」がないのはなぜか。土に「術」は通用しないからだ。 日本でもある時期まで、「芸」と「術」は厳然と区別されていた。だから今でも、「芸」しか通用しないものは(しかたなしに)「芸能」と呼ばれる。 「芸」と「術」の転倒した時代が江戸幕府瓦解以後始まる。いや、瓦解させるためには、転倒させる必要があったのだ。「芸」に「術」がついたものが尊ばれるようになるのは、じつに意図的な行為であった。 もちろん、そうしなければ、日本は西洋にいいようにあしらわれ、壊滅していたであろう。 しかし、その事実こそが、「術」を尊ぶことになったことを如実にあらわしている。 私たち、自分が日本人であると意識している者たちにとって、(明治以降から続く)現代は、まさに「術」の世の中なのである。 だから「芸術」は価値があり、「手術」できる者は尊敬され、「処世術」が人々の気をひくのである。 しかし、実際に楽器演奏に携わってみると、「術」の入りこむ余地はほんのわずかしかない。ほとんどが「芸」で成り立っていることがわかる。西洋の多くの優れた音楽家は、まさしく「芸」によって、現代にもその存在が続いているのである。そして、それが「芸」であることを裏付けているのが「技」なのである。 「技」が恒常的になり、それを使う人間と不可分になったときに、「技」は「芸」と呼ばれる。 そして、それが「芸術」と呼ばれるとき、それは私たちの生活の中で認められつつも隔離されるのである。 (この項も続く) |
||||||
| 03/06/30 | 「Saving Private Ryan」のノルマンディーのシーンで、おびただしい魚の死骸が打ち上げられているその意味が、最近ようやくわかったような気がする。 これまでは、史実がそうであった、としか理解していなかったが、スピルバーグが意図したのは、その臭いだったのではないだろうか。 原爆投下後にいち早く入市した航空士官が、あの臭いだけはどうやっても伝えられないと語っていた。 それは、魚の腐ったような臭いだったそうだ。 血に染まったノルマンディーの打ち寄せる波と、累々と横たわる屍は、魚の腐ったような臭いを放っていたであろうと、類推される。 誰もこれまで触れていなかったが、スピルバーグは、映像の中に臭いを持ち込もうとしたのではないだろうか。それも、映像作家らしく、映像として。 |
||||||
| 03/06/21 | 音楽は「再演」されることを望んでいる。 シュトックハウゼンの「コンタクテ」や、ピエル・アンリの「ドアとため息のための変奏曲」を聴いていると、そう思う。 「再演」と「再生」は違う。 「コンタクテ」のCDは「再演」だが、ピエル・アンリのCDは「再生」だ。 それは、つまり、オリジナル録音か、再録かということになるのだが。別の見方をすれば、「ドアとため息のための・・・・」は「再演」可能かということになる。 こうした、ミュージック・コンクレート作品は、演奏と作曲とが、どう区別されるのか。 「演奏」が今現在音を紡ぎ出すこととすれば、「作曲」は未来に向かって音を紡ぐことになろう。 ピエル・アンリやシュトックハウゼンがアナログテープをダビングし、切り取り、貼りつける行為は、「作曲」だろうか? 「演奏」だろうか? そんなことは問題でなく、耳に入ってくる音(=聴衆=私たち、が聞く音)がすべてだという立場に立ったとき、 コンサートホールでCDを聴かされて、それでも私たちは満足するのだろうか? ライブ・エレクトロニクスの作品の多くは、その点に関する確執の結果であったり、妥協であったりする。 (ライブ・エレクトロニクス作品の可否は、また別問題で、今は、「コンタクテ」と「ドアとため息の・・・」の差異から何が見えるかという、思考実験である) (この項続く) |
||||||
| 03/05/20 21:53 |
昨年に引き続いて、エリザベト音楽大学で、吹奏楽コンクール課題曲の指揮講習会に行った。 二人の大学生、二人の教員が指揮台に乗った。 大学生は棒を振るだけで精一杯だったが、二人目の広大オーケストラの学生指揮者は意欲的で次第に良くなった。 教員の指揮は、ひとりよがりという印象。二人目は元下松高校の中井先生で、秋山先生からも絶賛の声しかなかった。 しかし、いったん秋山先生が振ると、まるで違う。 基本に忠実な明快な棒で、なおかつスコアのすべてが棒からわかる。それに加えて、楽員を引き込む力がある。 講習者が質問した時の説明の時の手の動きは、まるでマルセル・マルソーを見ているようで、動きにむだが無く、点から点へ動いているかのようで、まさに「棒一本」で世界を相手にしている人だということが伝わってくる。 初対面の楽団に対して、最初の一振りですべてを伝える技術と心がある。 私の指揮がそれでいいのだと、思う反面、学校教師の陥穽に陥ってはいないかと、とても勉強になった2時間あまりだった。 |
||||||
| 01/12/30 | 夢のセオリー 私たちはどのように夢を見るのか。 そして、私たちはどのように現実を見るのか。 数年前、私は、左頭部の軽い偏頭痛で夜中目を覚ました。 軽い目覚めのあと再び眠り、私は夢を見た。 通勤途中に通り過ぎる交叉点の横断歩道を歩いてわたっていた。(現実にそこを歩いたことはほとんどないのだが) 左折してきたダンプトラックが私を見つけてブレーキを踏んだが、間に合わず、私の左頭に軽く当たった。 それで私は、左頭部が痛かった。という夢だった。 つまり、頭痛という結果の原因を夢に見たのである。 すべての夢がそうではないにせよ、夢とは逆上ってみるものだ。一般的な夢の理論がどうであれ、こういう夢の見方もあるのだと思った。 「夢を見る」という時の「見る」と同じ意味で、私たちは現実も「見ている」のではないだろうか。 結果はすでにある。その原因や理由を逆上って見ているのである。 結果とは、私たちの体にある原生動物的反射であり、それを人間として正当化するために、理論化しているだけではないだろうか。 その意味でも、私たちは「現実を見る」のである。 |
||||||
| 01/10/06 | 広島MOTTO PARCOはやはりやばい ファッションについての話。これは、原体験、刷り込みの問題だろうけれども。十数年、いや、二十年、着たい服、したいファッションがなくなった。 先日MOTTO PARCOへ行ってみた。さまざまなファッションがあったけど、一緒に行った彼女はここにいると散財しそうと言ったけど、私が欲しかったのはネクタイ二本(千七百円・税別)だけだな。そのネクタイには、彼女は賛成しなかったけど。 その時に彼女に言ったことが、ここの趣旨。 私の時代は、正確に言うと私が自己を身につけた時代は、ユニセックス、モノセックスの時代だった。それは、今にして思えば、それほど性別が峻厳であったということだけれど。ユニセックス、モノセックスであることが、自分より一歩前の時代を否定することであり、一歩前の時代を否定することが自己の確立であった時代だったということ。 そのころの私は、女性のファッションをどう男性として取り入れようかと考えていた。男性が女性に近接し、女性が男性の領域に侵蝕する、そういう時代だった。 今は、もうそういう時代はとおり越して、女性であること、男性であることが、テーマになっているようだ。それはMOTTO PARCOだけの問題ではない。かつてのFROM USA、今のROAD RUNNERにしても、もはや私の興味を引くものはない。 たぶん、これは、時代の進歩というものだろうけれども。 たしかに、男物はよりガーリッシュに、女物はよりマニッシュになっている。そのうえで、男であること、女であること、というテーマを追っている。社会的に性差がより少なくなってきたために、かえって性差が見えやすくなったのか。 これまでになかった新しい存在を身にまとうという、ファッションの命題が、消えてしまったような気がした。もはや、ミニスカートにルーズソックスという、時代遅れの女子高校生ファッションを、だれも笑えない時代になってしまっている。 寝付きの悪い私だが、もっと寝付きの悪い寝付きを、昨夜は経験した。 ちなみに、あのネクタイは彼女に内緒で買って、彼女からは、彼女ご推薦のネクタイをプレゼントしてもらうことにしよう。そして彼女には、ゴダールの「中国女La Famme Chionese」を見せてやろうか。 もう一つの話題は、ジャズの悲劇についてだった。 単なるポップスであったはずのジャズが、個人芸を追究する演奏になった結果、演奏家と聴衆の間に、意識されない引き裂かれた関係が生じたということ。 どんなに個人芸を追究する演奏家がいて、それを支持する聞き手がいようとも、ジャズは、その始めから、消費される音楽としてしか存在しえないし、存在していない。現代音楽の閉じられた開き直りと対照的に、開かれた矛盾がそこにある。 TOWER RECODSのジャズ・コーナーで、適度にアルコールに浸された私は、悲しくCDたちを見ていた。 |
||||||
「経済」について。 「経済」とは「物」の移動であると言える。「貨幣経済」は、そのうちの「物」と「貨幣」が逆方向に移動することと言える。(fig.1) つまり、「物々交換」であれば、「物A」と「物B」が逆方向に移動することになる。 「贈与」であれば、「貨幣」ないし「物B」の量が無限に少なくなることになる。 「経済」とはその基本原理は案外簡単に説明できる。 fig.2はデフレーションの、fig.3はインフレーションのモデルである。 従来、インフレーション、デフレーションの定義は、需要と供給の関係で語られてきたが、高度生産社会である現代では、需要は供給によって作られるという様態が形成されているので、需要と供給が循環関数で存在しているのである。 こういう社会においては、インフレーションとデフレーションはfig.2および3のモデルでしか語ることはできない。
|
|||||||
イナーシア(慣性)
たった今、「24時間テレビ」の研ナオ子の24時間マラソンの番組があり、また、辺見庸自身が「不安の世紀から」で日本人が失ったものの一つとして「家族のきずな」をあげているが、私たちはそんな物は持っていなかったというのが、落合恵の示唆するところであったと思えば、研ナオ子の家族観も辺見庸の家族観も、同様なものであり、欠落感の表象として同等であり、それを図示すればfig.1のようになるのではないか。fig.1において、「慣性」とはそのまま辺見の言う「イナーシア」であり、「重力」は辺見の言う「肉体性」に当たるであろう。そうすれば「自由落下」はリフトンガ言い辺見が賛同した「プロテアニズム」ということになるだろう。 もちろん、辺見にすれば私の感覚が間違っていることになるだろうし、辺見の論証に100%近くの同意を感じるのであるが、私たちが失ったと感じている物は、じつはいつの時代にも私たちが持っていなかった物である。その意味で言えば、価値観の喪失、神話の崩壊、なんとでも言えるが、幻想がなくなっただけである。 −−私はたんに、辺見の世代の「物言い」にうんざりしているだけなのかもしれない。曰く、「彼らは異議を唱えるだけである」。 彼に対する「文句」はもういいだろう。発展的でも生産的でもない、「文句」だから。−− じっさいのところは、fig.2に示されたように、「慣性」は常に重力方向へはたらいているのが、私たちの日常であろう。この重力を構成する物は容易ではない。私たちの怠惰な感性や、盲目的な従順がすでに肉体的レベルにまで達しているからである。 辺見の言うように、「肉体」と「感性」を弁別して、脂肪分のこびりついた「肉体」を洗い晒さねばならないのだろう。 もちろん、私たちは「去勢された牝猫」であることであろう。 |
|||||||
| 01/03/27 21:14 |
SONYのCM、「あなたの[ ]がコンテンツになる」。 今私達は、個人から世界へ発信するチャンスを手にしている。 自分の私生活、家族のこと、恋人のこと、結婚したこと、子供が生まれたこと、子供が成長したこと。 発信が、もはや表現というフィルターを必要としなくなってきた。 やがて、私達は私達を監視する世界を手に入れる。 真面目で一本気な人間も、いい加減で人を欺く質の人も、表現の本質「だけ」を手に入れる。 |
||||||
| 01/03/26 22:53 |
岡山県邑久町の殺人を犯した17歳の少年のこと。 たしか、逃亡中に攻略本を読んでいたと覚えている。 そのことの意味は。 下記の文章と関連性は、あるのではないだろうか。 |
||||||
| 01/03/26 22:46 |
「経済」とは「物の流通」であり、「流通」とは「移動」である。 日本において子供の人権の意味は、そのように捉えられる。 (以下雑感) 「バブルが弾けた後」でも、経済が「子供の経済活動」である限り、本来的な解決にはならないのは明らかではないか。 |
||||||
| 01/03/19 22:36 |
昨日は、午過ぎまで寝て、古江の竹葉庵に昼食を。 あれはなんだろう。やはり狸なのだろうか? それから帰宅して、しばらくまた寝た。 わたしはこの二つを一つのことのように考えた。 春のみょうに白っぽい一日には、そんなこともあるのかもしれない、と思わなくでもない。 この一文、昨日の一部始終を正確に記したわけではない。 |
||||||
| 01/02/21 23:12 |
潜在的にあった意識の中の駄洒落。 「時間」の問題、「物質」の問題、「意識」の問題、簡単に言えば「存在」の問題、 |
||||||
| 01/02/11 01:27 |
「死者」が私(たち)に語りかけてくる、って、それは「霊」の「存在」ではないよな。 |
||||||
| 01/01/15 00:14 |
蘚苔類、地衣類、菌糸類、 『旅する種子』を書いてから、植物についてはわかってしまった気になっている。 もちろん、学問的には何もわかってはいない。 でも、わかったんだもん。 どうわかったかの説明が、あの詩集。 落合恵美子の『近代家族の曲がり角』で、人口学的な研究や、ネットワーク的な分析を読んでると、つくづく人間って植物的だと思う。 あの詩集で正解だった。 まあ説明的な説明でないので、わからない人にはわからないけど。 で、次は、蘚苔類、地衣類かと思ったけど、これらもやはり植物なんだった。 菌糸類・・・? 黴や茸? 大きくは植物なんだろうか。 もっと何かがある。私たちの在り方を指し示す何かが。 |
||||||
| 01/01/15 00:04 |
また柿の話。 果物で、甘いだけの果物ってある? りんご。いちご。ばなな。 (私にとって?)古典的な果物は、どこかに酸味があるよね。 あるいは、かつては酸味のあるものだったよ、ね。 そんな中で、柿は唯一甘いだけ。あるとすれば、渋み。 やっぱ、不思議だわ。 で、やっぱり食べたいと積極的には思わんなあ・・・ 懐かしい感じはあるんだけどね。 あ? 食べたいかもしれない。 |
||||||
| 01/01/02 02:42 |
有名な「香炉峰の雪」の段。 さして美人でもなく、スタイルがいいわけでもなく、男にちやほやされるわけでも、男と気安く口をきく質でもない。 てな具合に、だんだん同化していくのであった。 |
||||||
| 01/01/01 20:31 |
主語がない 「キレル」、「ムカツク」。主語がない。 「切れる」のは「堪忍袋の緒」、「むかつく」のは「胃」、「焼ける」のは「胸」と決まっている。 「自分は・・・自分は・・・キレちまったんです、神経が。」(ヨハン機関士:『Uボート』;字幕ママ) 「主語」というか「動作の対象」というか。 日本語は「主語」を明確にしない言語だというが、それはある状況の中で明らかに明らかである場合である。 |
||||||
| 00/11/20 22:33 |
柿は嫌いじゃないんだけど、なぜか好きじゃなかった。(これって、嫌い!ってことぢゃん) ようやくわかった。 あのぬるぬる感が嫌なんだ。 さく、とか、しゃく、といった歯触りがないのが嫌だったんだ。 同じぬるぬるでも、マンゴは許せるのはなぜだろう? 蛋白質分解酵素の多寡なんだろうか? 酸味なんだろうか? そういえば、柿に酸味って、ないよね。甘みだけ。 はてはて。 |
||||||
| 00/10/16 01:37 |
じつは、「根無し草」の感覚を、「この土地」に定着させるためには、大いなる空虚が必要なのかもしれない。 みなの「幻想」を吸い寄せ、満足させるだけの、広大な空虚が。 「天皇制」がいつ変容したのか。 「大化改新」。 「明治維新」。 いずれも、「空虚」を発見し、活用する運動ではなかろうか。 「空虚」はつねに、「利用」されるためにある。 それはあたかも、ビル街の空き地のように、次のビルが建つまでの間駐車場として利用されるように。 日本の土地神話の根元は、じつはこんなところにあるのかもしれない。 |
||||||
| 00/09/20 01:32 |
時間が空間化すること。 何も難しい話をするわけではない。 二千年前の日本を空想すること。である。 広島の町中から、中国山地中の村落へドライブすること。 じつは、時間は空間化しない。 広島の町中も、中国山地中の村落も、同じ時間を過ごしている。 私は「文化・文明」の伝播について考えようとしている。 二千年前の日本列島も、黄河流域の中国も、同じ時間を過ごしていた。 中国山地中にゲーセンがないのは、それを受容するに足るだけの人口がないだけだ。 また、それを受容するだけの生活形態がないだけだ。 中国山地中にゲーセンを作ったって、ほんの一週間でつぶれるだけだ。 それをむりやり持続させたのが、大和朝廷・・・か? とすると、その膨大なエネルギー、そして、いまだに続く根無し草の感覚には、唖然とせざるを得ない。 |
||||||
| 00/09/01 23:34 |
言葉は、大気のように私(たち)のまわりにある。 その「言葉の大気」の手触りは、柔らかな粘土のようでもある。 そこに、指先で、あるいは釘の先のようなもので、引っかき、あとをつける。 大気は循環し、私のつけたあとは、さまよいまわる。 私のつけたあとは、少しずつ変形してさまよいまわるが、それが私のつけたものであることに変わりはない。 そんなふうにして私の言葉は流通していくのだろう。 |
||||||
| 98/10/25 21:10 |
昨日。わずかに紺がかかったベルベットの空に、明るい三日月がかたむいていた。 その後。空は黒繻子の深さに変わり、三日月は変わらぬ明るさを保っていた。 今日。空はうすぎぬのなめらかさに、昨日と変わらず月をかたむかせている。 私たちが感動するというのは、その対象の「思い」ではなく、「物」ではないか。 言葉は、「物」ではないにしろ、「現象」であろう。 |
||||||
| 98/09/16 01:46 |
>不安さえもが、私たちを救い出すのだ。 不安とは、それを感じようとしなければ、不安ではないだろう。 そしてしかし、一度感じてしまえば、それは「不安」として正当に私たちの中に存在しようとする。 「ものは思いよう」 人は言葉によって不安になり、言葉によって不安から救われる。 しかし、状況は、何らの変化もない。 酒精がその不安から私を救うのは、言葉と状況の絡みぐあいを曖昧にするからだろう。 私たちは何も持たずに生まれてきた。 「生命」や「意識」でさえ、それは私たちが望んだり努力したりして手にしたものでもなく、また誰かから与えられたものではない。 とすれば、それらを失うことは、私からそれらが失われることと、本質的に離れたことがらだ。 私にはもともとそれらがなかったのだから。 私たちが生きているということは、錬金術師が科学者へと変貌し、物質の反応を楽しみに眺めているのに似ているようだ。 私は私が醜いと思い、また美しいと思う。 あるいは、大きいと思い、また小さいと思う。 その相対性は、私たちがそれらを私たちのものとして持っていないことにつながっているのではないか。 私は「Mission Impossible」のある回を思い出す。 体と同じ比重の液体に浮かばされ、耳も鼻もふさがれ、つまり、自分外の存在を感じ取れない状況に置かれることが、この上ない拷問になる、という話。 不安は私たちを狂気(不安定さ)へとみちびくきっかけとなるが、不安のなさは、私たちを存在が本質的に持っている不安定さに浸り尽くすことになる。 空腹感は私たちに生命の危機を感じさせるが、恒常的な満腹感は私たちに存在の空虚さをウイルスのように植えつける。 だから「空腹」でいろ、とは言わない。 「満腹」であることからくる空虚が、私たちの存在を風船の中の空気のように膨らませているのだから。 これらのことを、「物質的<->精神的」自立の問題として語ってはいない。 これらのことは、私たちの本質的なことなのだから。 空腹の時は、私たちは自分たちの空虚さを忘れさせられているだけなのだ。 空腹を満たそうという、反射的な欲望の突き動かす中だけに、私たちは存在しているのではないか。 私たちは、錬金術師から科学者へと変貌する正当な道筋をたどっているだけだ。 |
||||||
| 98/5/16 01:01 |
「言葉」が記号化したという話がされた頃から、10年はたつにちがいない。 言葉は今どこにあるのか。 一時期、私の中で、言葉の記号化の問題が緩和されていた。 今、「詩」はどこにあるか。 言葉の中には、私たち人間の不可解さが、人間存在のわからなさが、こめられてしかるべきだと思う。 言葉が語るものは、人の思いなどでなく、言葉そのものだということを、もう一度確認したい。 安易に、言葉の奥に人の心があるとは思ってはならない。言葉は言葉のみを伝えるものだ。 そういう認識からしか、切実な言葉は生まれ得ないだろう。 もどかしさ。焦燥。正当性への憧れ。・・・・・そうしたものからしか、言葉を越える言葉は生まれ得ないだろう。 私たちは、ものごとが言葉によって明らかにされる行程を知っている。それと同時に、明らかにされ得ないものが、明らかにされたものの背後に亡者のように蠢いていることを感じているはずだ。その感じを明らかに感じるか、どうか。 言葉は、迷路を歩み進むためのか細いロープに過ぎない。その端が出口に固定されているとも限らない。途中で断ち切られているかも知れない。 それらのことは、歩みを進めるために手に持ったロープの感触からしか、うかがうことはできない。 言葉の端が、確実に迷路の出口に結びつけられているか、どうか。そうした不安をもう一度持たねばならない。そして、不安であっても、私たちは「ここ」にロープの端を握ったまま立ちつくしていることはできない。いずれは餓死してしまうだろうから。 私たちが手にしたロープの、もう一つの端の感触を、手元からだらんと地面に垂れ下がった(不安定な)重みから知ろうとすることが、私たちの言葉に対する勇気を与えてくれるだろう。ロープを持っていることが私たちを迷路の出口へ導くのではなく、手にしているその反対側のロープの端を想像することが、私たちを救い出すのだ。不安さえもが、私たちを救い出すのだ。 |
||||||
| 98/3/30 00:49 |
人がものを食べるとは、何なのだろう。 昨夜KIYOのカウンターの端っこの席で、隣の中華「桃園」で中華そばを食べている人を見ていた。 友人と喋りながら食べるその中華そばは、古くなったゴムのようにぱらぱらとその人の口からこぼれていった。まずそうに見えた。 今夜テレビのドキュメンタリー番組で、2度食事の場面が映った。 その家族は、義務のように食べていた。 人がものを食うことは、かなしい。 私たちは、物質を、食べるという行為によってしか、自分の体に変換できない。 |
||||||
| 98/03/09 22:15 |
>「詩」が表すことのできる「真実」とは、現象としての言葉の中にしかないのではないか。 現象としての言葉、と私が言うとき、言葉と私の関係はどうなっているのか。 言葉は私にとって、「関係」と呼ぶしかないように、どこまでも他者なのだろう。 言葉を見つめること。 ・・・・・私は言葉を(肉体の一部として)発することから生まれながらに隔離されている。・・・・・これは「にほんご」の特性ではあろうが。 にほんご表現の枝分かれの(袋小路的)行き止まりに、私はいるしかないのだろう。 このところとうぶん詩表現をなしていないが、最近今にも折れそうな枝先に私は爪先立っていることをかんじている。 |
||||||
| 97/09/15 01:47 |
『易経』の精神とは、全ての変化は「宇宙」の変化に基づくことに尽きよう。 逆に言えば、ほんの小さな変化も、それは「宇宙」の変化へと遡ることができる。 ミクロを見つめることでマクロへ到達でき、それはまた別のミクロへと敷衍できる。 私の「詩」は、そのような詩になり得るのだろうか。 私に見えるのは「ミクロ」でしかない、「マクロ」は見えない。 であれば、それしか道はないではないか。 |
||||||
| 97/06/30 01:09 |
「この世」の「真実」は、何だろう。「真実」はあると、私は思いこんでいる。 「言葉」によって、「真実」が表現できるか。 「言葉」とは「意味」であり、「意味」とは「代理」であれば、「真実」を「表現」する事はできないのではないか。 「詩」が表すことのできる「真実」とは、現象としての言葉の中にしかないのではないか。 そのために、私は「RFG」を使用し、自分の恣意による言葉を拒否しようとする。「言葉」によって「意味」を伝達することを拒否する。 「現象としての言葉」とは何か。 行為としての言葉。 「意味」を意図しない言葉。 |
||||||
| 97/05/09 23:51 |
たとえば、花の生活と私の生活が交差するところとはどこであろうか。 私が花の生活を収奪しないことは、何であろうか。 私の生活は花の生活と交差しない。 そのことに何の意味があるのだろう。 萎びた感性が私のシナプスからシナプスへとつらぬいているのだろうか。 |
||||||
| 97/05/08 22:22 |
魚の内に、私は生まれたのだろうか。 このままで敷き詰められた輝きの上を泳ぎ切ることが、 私の動きを縮めるであろう。 |
||||||
| 97/05/08 20:23 |
詩人は、ものを見る目だと、稲方正人の新作詩集を読んで思う。 それはそうだろう、自分が詩を書こうとする時、自分が何を「見て」いるのかまったく分からなくなる。 目の前にあるのは、ノートの表面であったり、PCのディスプレイであったりする。 (その意味で、PCで詩を書くというのは無謀な話かもしれない。) いや、そうではないかもしれない。 ペンで、紙面に詩を書き留めたのが自分にとっての原体験であれば、紙面の滑り具合や、ペン先の固さや、インクの染み具合が私に官能を与えていたことを、はっきりと思い出すことができる。 こうして、PCのディスプレイに向かって、キーボードをたたいていると、横のTVの画面に目を奪われていても、いわゆる「ブラインド・タッチ」で言葉をつづることができる。 私の「官能」はどこにいったのか。 音楽は、その「行為性」の中に存在意義がある。と感じている自分にとって、言葉を「書く」とことの官能性は、その行為の中にのみあると意識してもいいはずだ。 PCのキーボードを叩くことは、「ものを書く」という行為とは距離がある。 そこには直截な言語がある。 フォントにしたってそうだ。自分はゴシックで書くわけでも、明朝で書くわけでもないのに、画面には、設定で指定したフォントで文字が現れる。そこには自分の字はない。 それが、「言葉の本質」により近づいた形であるとは、よく分かる。 「言葉の本質」は、誰にも、いつでも等価である、ことにあるのであろう。書体や、声質や、その他諸々の肉体による制限から離れたところに、「言葉の本質」があるのであろう。 ところが、「詩人は、ものを見る目である」のならば、肉体性から離れたところで詩がどうなりたつのだろうか。 PCのキーボードが肉体に直結している人たちが現れているであろうことは、想像に難くない。 自分にとっての肉体性は何なのか、という問題なのだろうか。 |
||||||